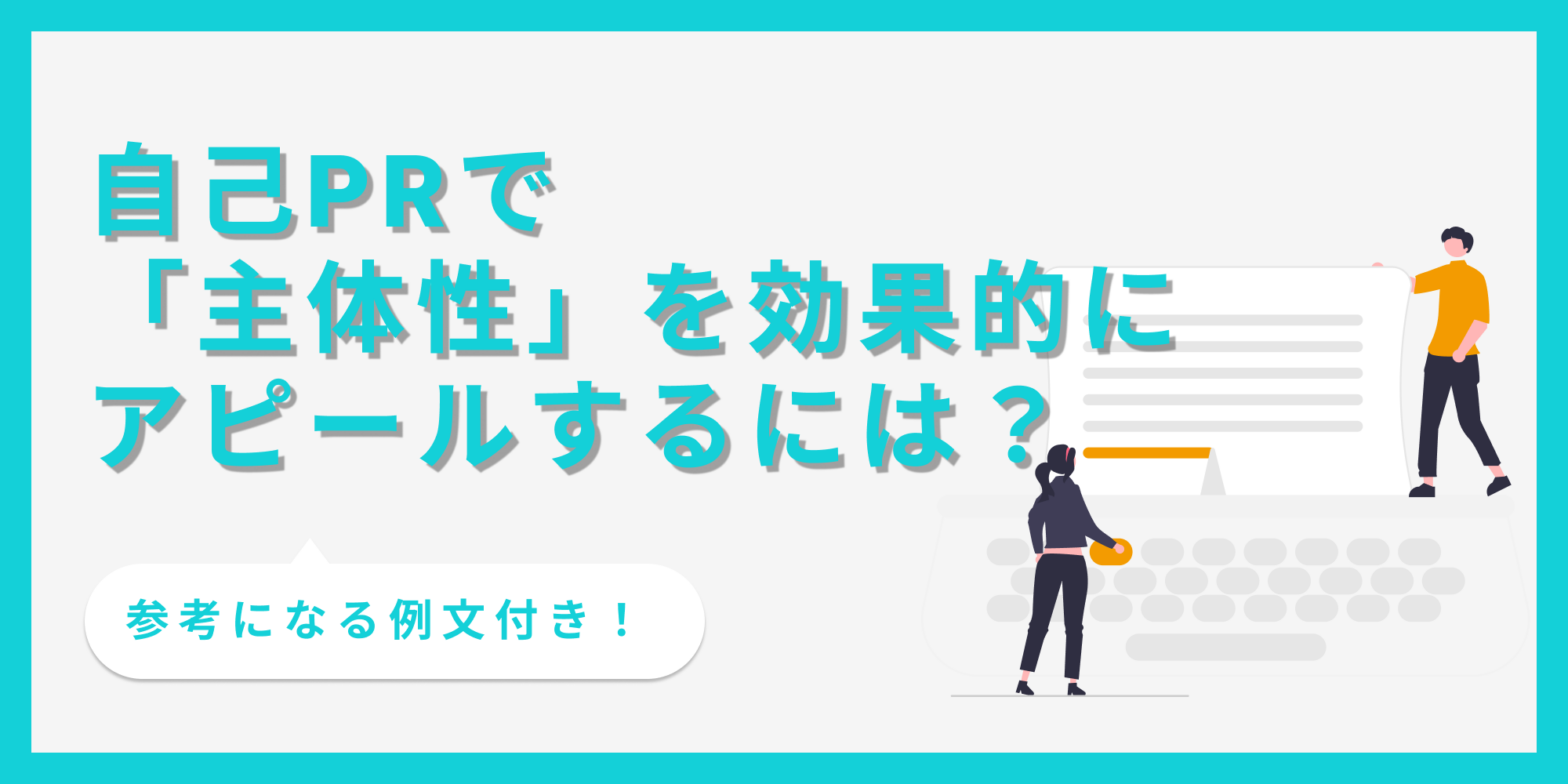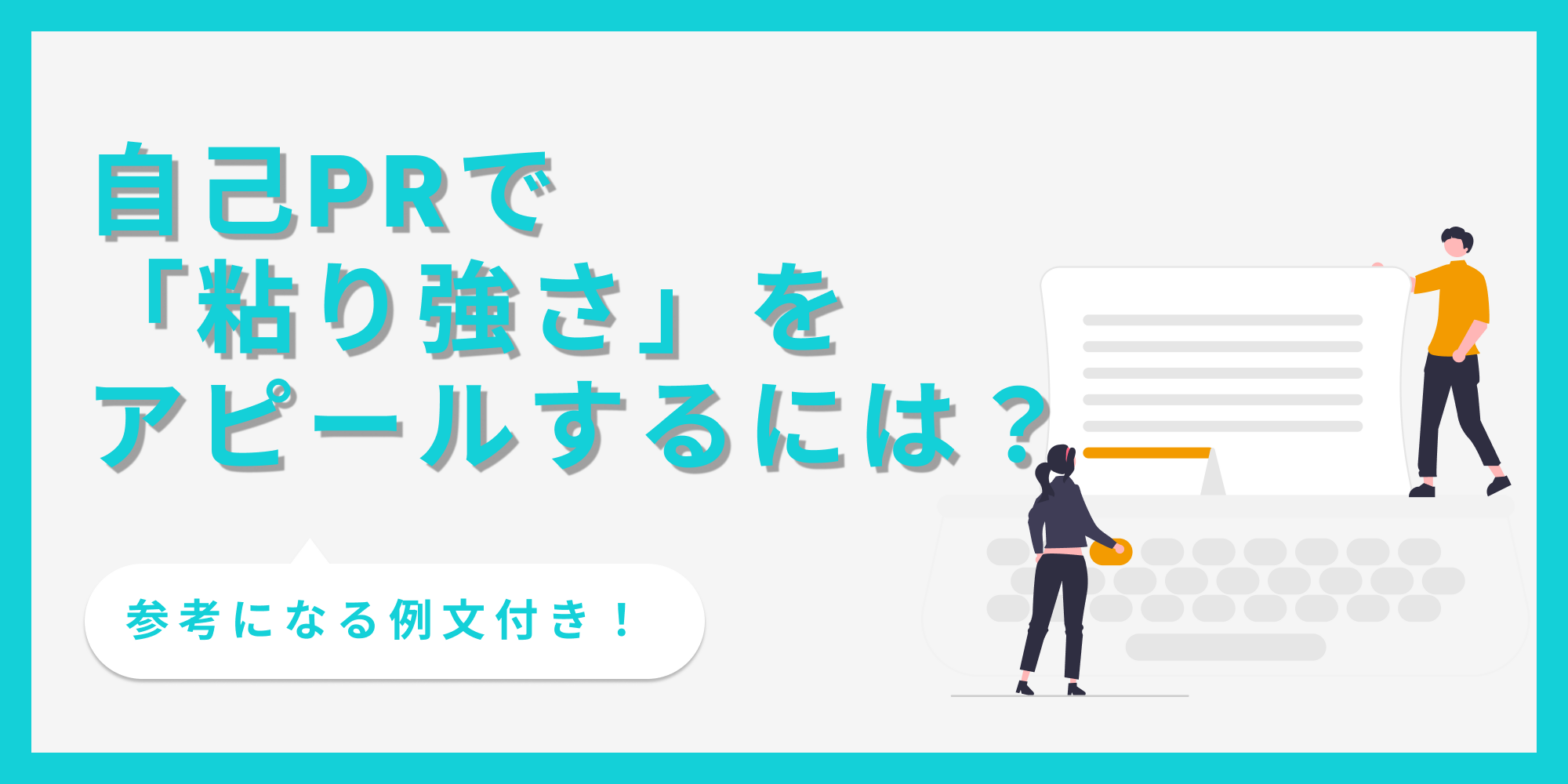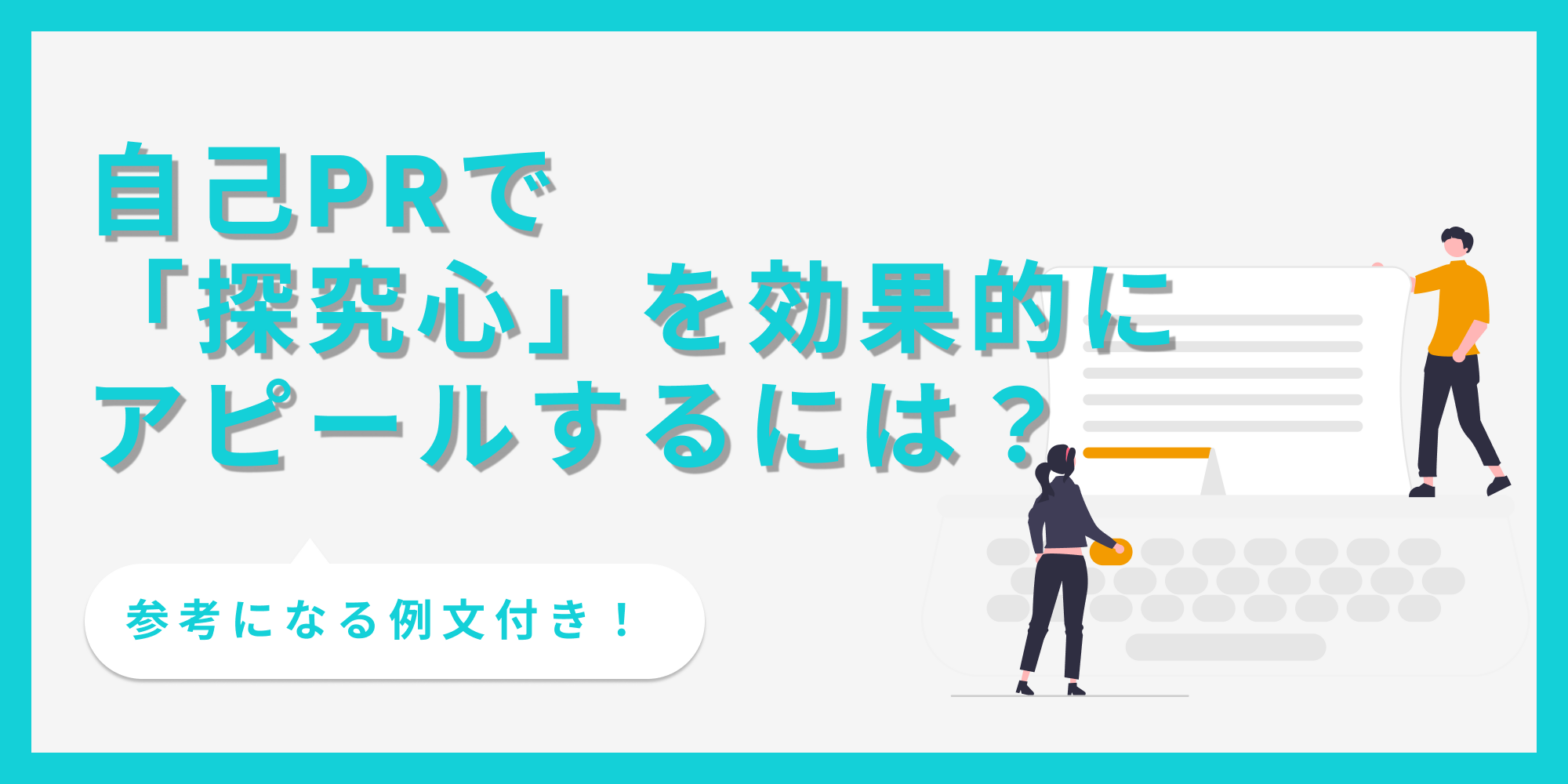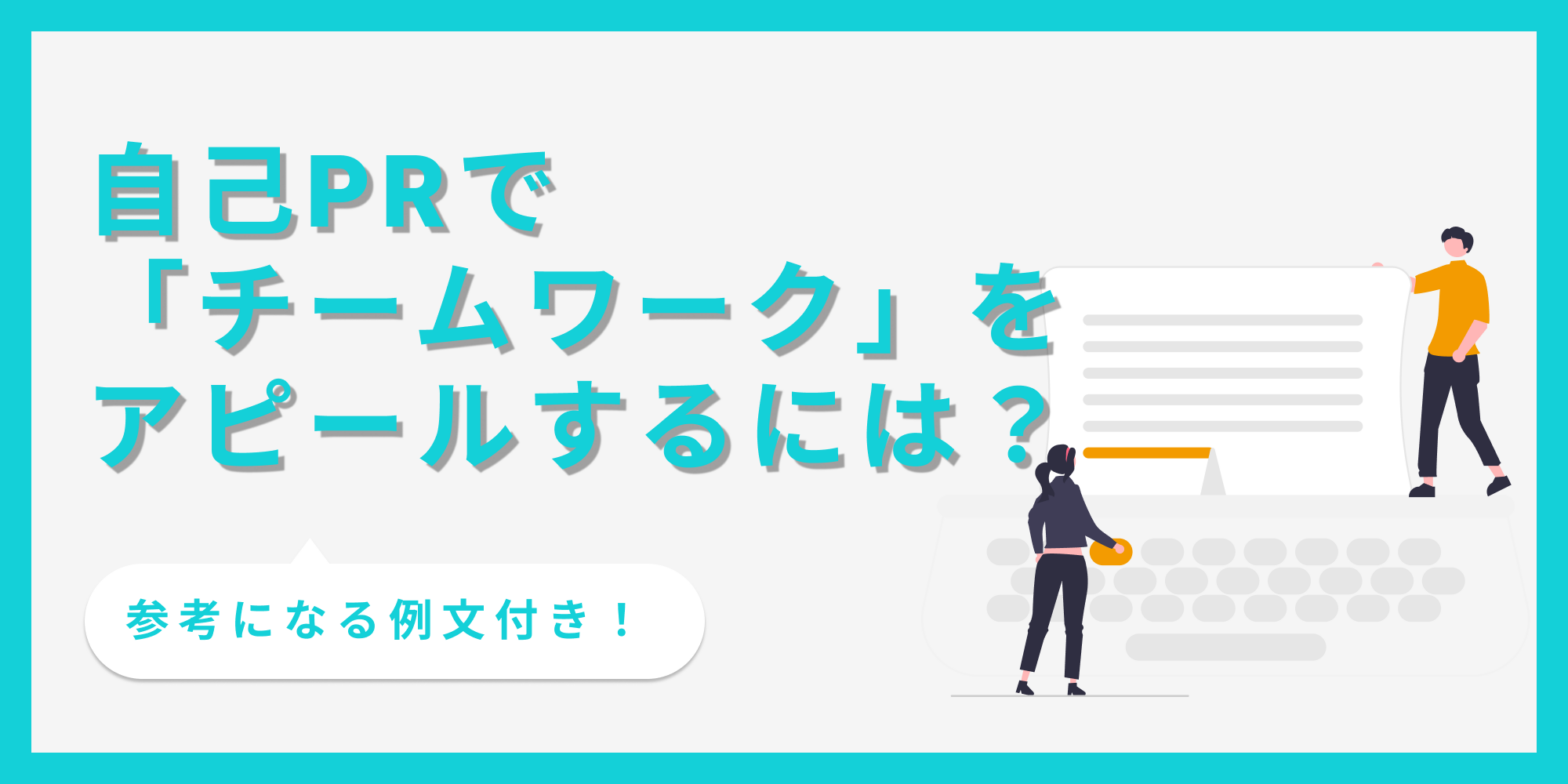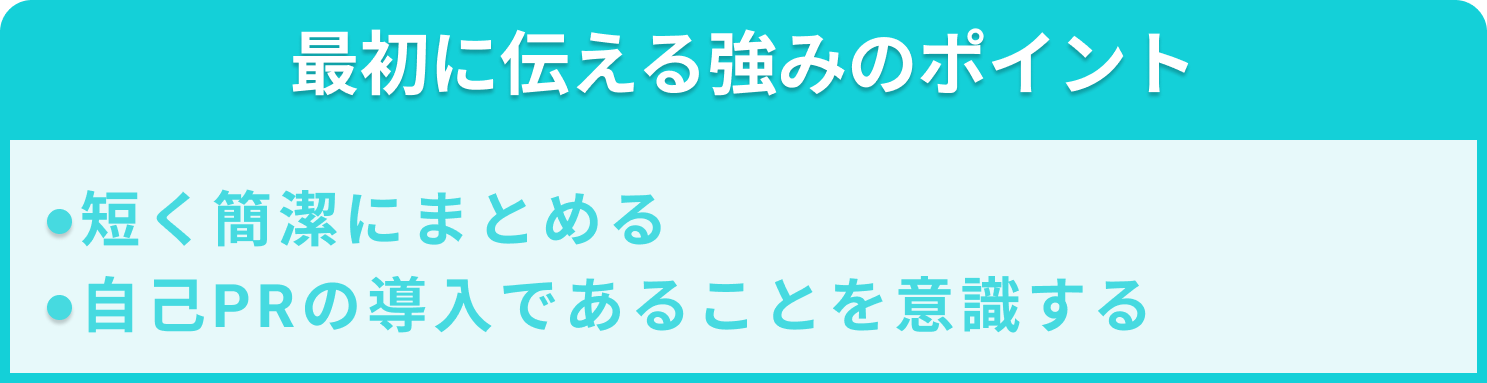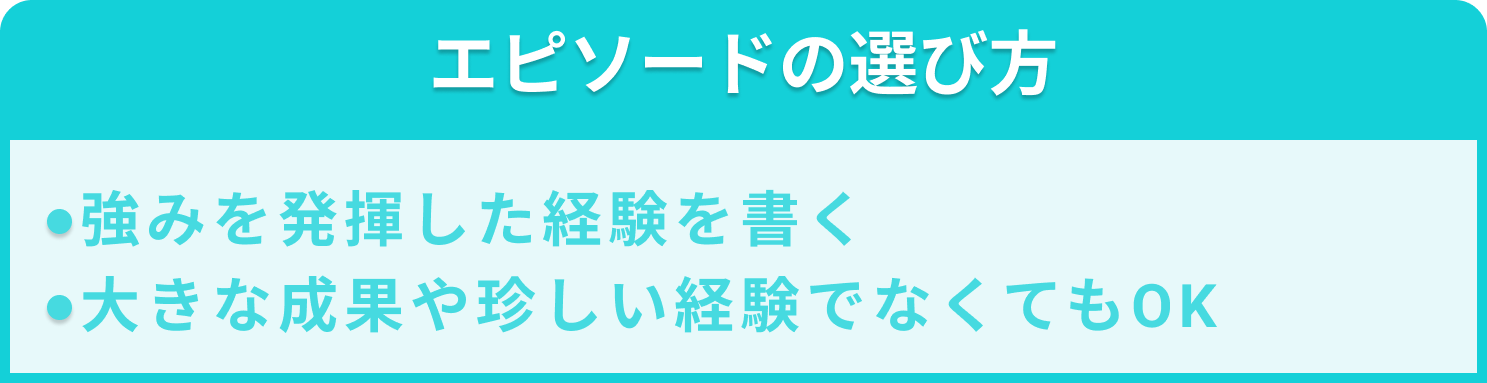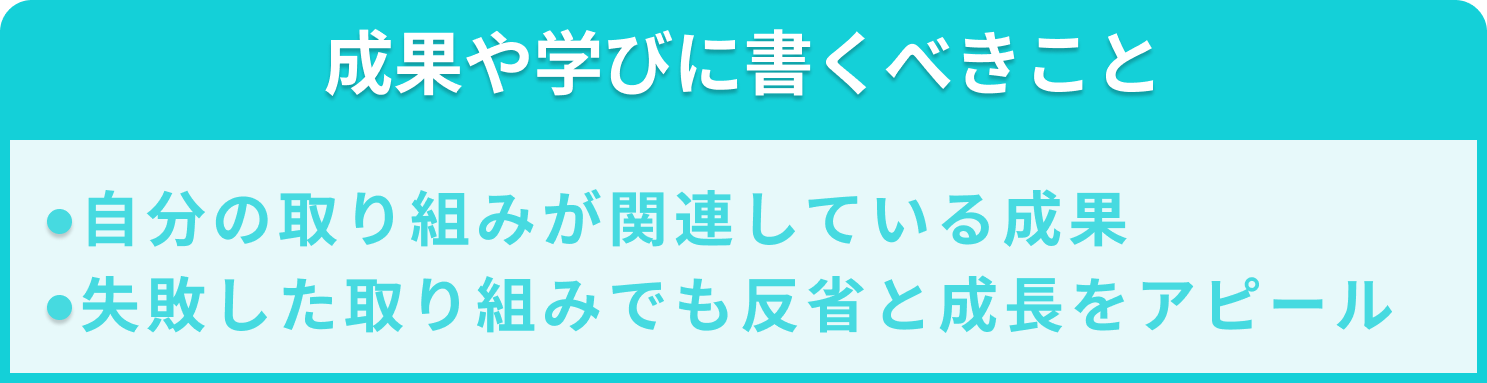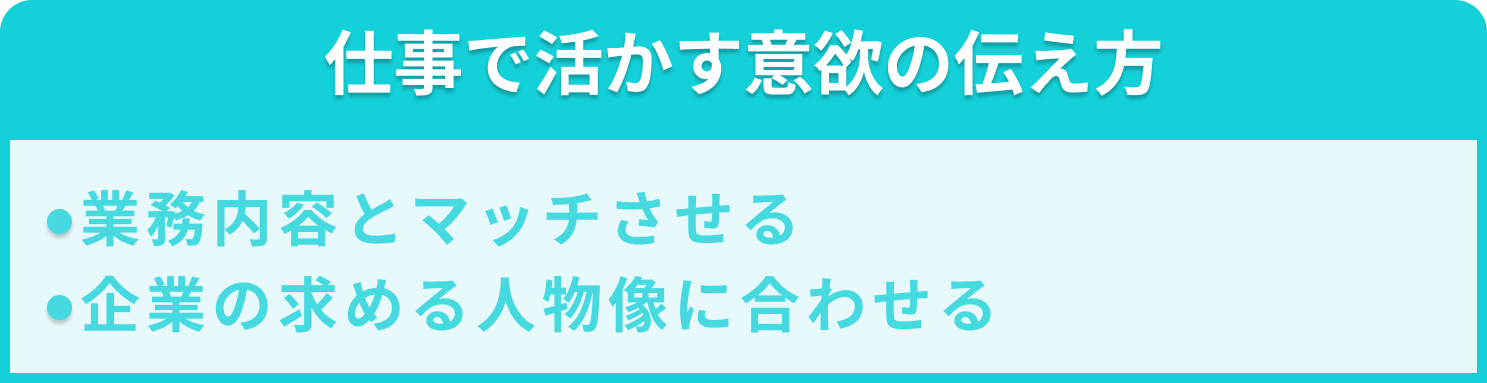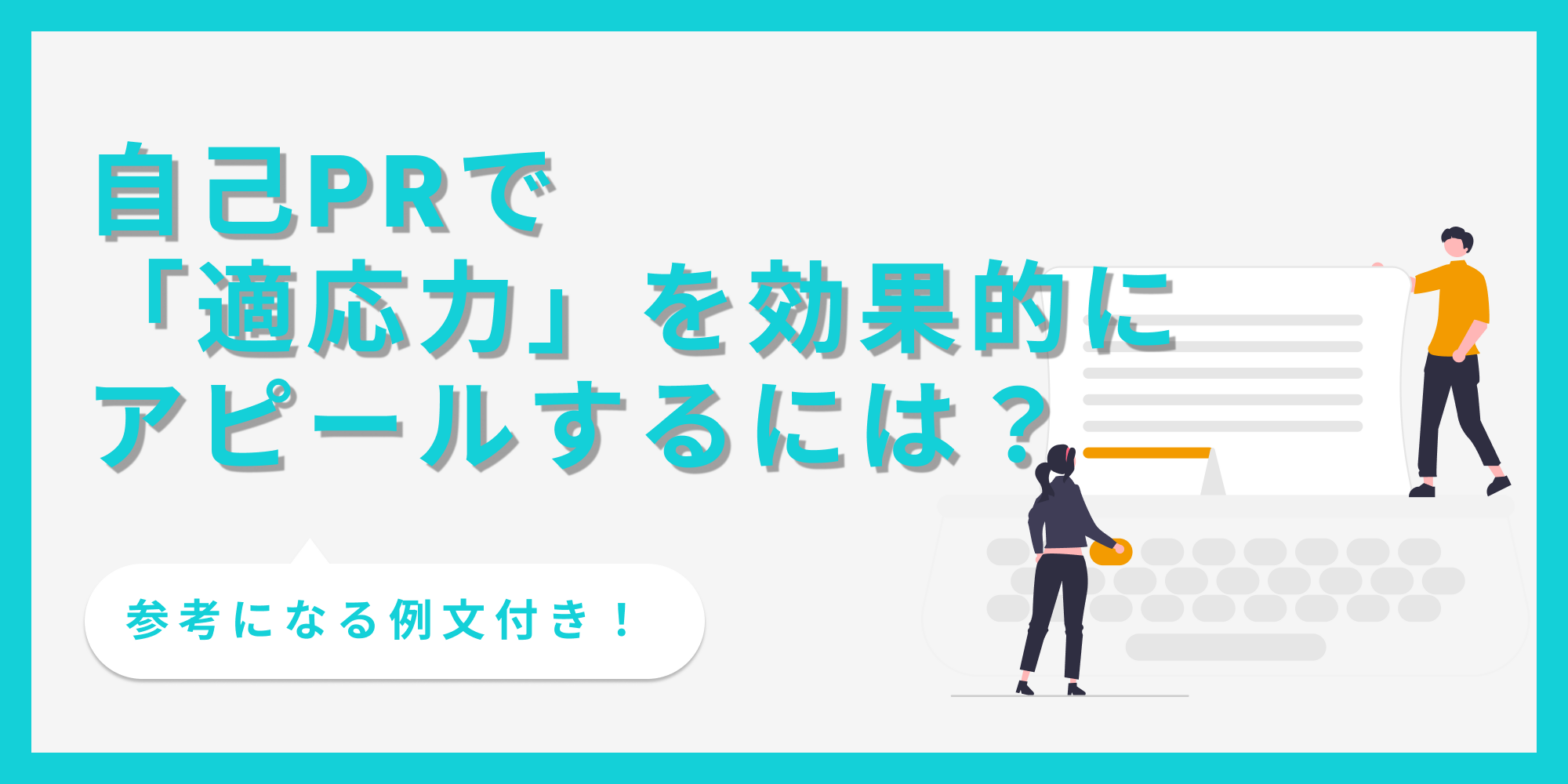ESのコピペはバレる?
コピペとは“コピーアンドペースト”の略で、ネット上にアップされた文章をそのまま自分の文章として使い回すことを意味します。
結論から言うと、ESをコピペで作成することはNGです。ESをコピペすると、高確率で採用担当者にバレます。採用担当者は大量のESを目にしてきているので、言い回しや単語がしっくりこないと、コピペしたことをすぐ勘づくそうです。
コピペすればESを準備する時間を節約できることに加え、「時間がない」「文章力に自信がない」という人にとって魅力的な方法かもしれません。実際に就活情報サイトやSNSには、内定をもらった人たちのESも多数公開されているので、採用されたいという想いからコピペしたくなる人もいるでしょう。
もちろん、内定者のESや就活サイトの例文を参考にし、同じような構成や部分的に同じような言い回しを使うこと自体は問題ありません。しかし、一言一句コピペしたESは見破られてしまいます。コピペがバレれば、就職への熱意が伝わらないだけでなく、企業の信頼を失って不採用になる可能性もあります。
ESをコピペするのは簡単ですが、デメリットの方が遥かに多く、選考結果へのダメージも深刻です。ESの「コピペはバレる」ということを心得て、一言一句そのまま活用することは控えるようにしましょう。
ESをコピペするメリット
企業の求める人材に合った内容になる
志望企業の内定者のESをコピペすれば、その企業の求める人材に当てはまったESを作ることができます。
ESを書く前の業界研究や企業研究の時間も短縮でき、的外れな応募書類を提出するリスクを回避できるメリットがあります。
内定者のESを参考にすることで、志望企業が好むESを効率よく作成することができるでしょう。
面接対策に時間を使える
就職活動中は忙しく、気がついた時にはESの提出期限が迫っていた!という経験がある人も多いのではないでしょうか。
ESをコピペで作成すれば、応募書類の作成にかける時間を大幅に短縮することができ、面接対策や説明会やOB・OG訪問、企業研究、Webテスト対策など、他のことに時間を使うことができます。
就職活動を効率よく進めるために、ESをコピペして使っている人もいるようです。
幅広い業種・企業を受けられる
ESをコピペすれば業界研究・企業研究に割く時間も節約できます。
その分たくさんのESを作成できるので、応募する企業数や業種の幅が広がるというメリットがあります。
異なる業界や業種を受けたいと思っている人でも、ESをコピペすればそれぞれの企業にあったESをすぐに準備できるでしょう。
ESをコピペするデメリット
熱意が伝わらない
コピペされたESは、応募者本人ではなく他の誰かが作成した文章です。他人の言葉では応募者の本心が伝わりにくく、採用担当者の心を動かすことはできません。
特に新卒採用の場合は応募者の人柄や熱意、やる気が重視される傾向にあります。
ESがコピペだとバレれば、「やる気がない」「考える力がない」と判断されてしまうでしょう。
オリジナリティがない
ESに書く志望動機や自己PRは、過去の経験をベースに自分の特徴や強みを書くのが基本です。
自分と似たような経験をしている人のESをコピペしても、感じ方や表現の仕方は人によって異なるため、自分らしさを際立たせることはできません。
コピペされたESでは、本来の自分の魅力を最大限に伝えるのは難しいと言えるでしょう。
バレたら信頼を失う
ESをコピペしてそのまま使った場合、「盗作」と捉えられてもおかしくありません。
新たに迎える新入社員が他人の文章を丸パクリするような人だったら、採用担当社はどう感じるでしょうか。ESのコピペは採用担当社と応募者の信頼関係を壊すきっかけになり得ます。
コピペがバレれば、問答無用で不採用になることも覚悟しておきましょう。
コピペはなぜバレるのか?
コピペチェッカー
コピペチェッカーとは、文章中にコピペされた部分がないか、既存の文章と酷似している部分がないかをチェックするものです。
コピペチェッカーを使えば、コピペされた文章がどのサイトのどこに書いてあるかまで確認することができます。
複数のサイトからコピペした継ぎ接ぎの文章であっても、その事実を見抜いてしまう優れものです。
企業によってはそれぞれ基準を持っていて、コピペチェッカーの結果が◯◯%以上のESはコピペ、◯◯%以下は独自で作った文章と判断軸にすることもあるようです。
コピペチェッカーを使えば、コピペ元が簡単にバレてしまうということを心得ておきましょう。
面接の深掘り
コピペしたESで書類選考を突破できても、面接で苦戦する可能性も十分に考えられます。面接では、応募者個々の魅力を引き出そうとESの内容を深掘りする質問がなされます。
過去の経験や具体例を詳しく聞かれた際、自分で作ったESでなければ上手く返答することができません。
スムーズに答えられなかったり、表面的な回答になってしまうと「自分で書いたことを理解していない?」「本当に自分で書いたのか?」と疑念を抱かれてしまいます。
コピペしたことがバレれば、せっかくの時間が無駄になったと採用担当者を落胆させることになるでしょう。
就活サイトや就活本
採用担当者は、就活サイトや就活本を一通りチェックしてから採用活動に臨んでいます。そのため、内容をそのままコピペすれば、採用担当者にすぐに見破られてしまいます。
志望動機や自己PRの例文は当たり障りのない内容のものがほとんどなので、コピペしても個性が感じられず、読み飛ばされてしまうでしょう。
採用担当者は様々なところで情報収集していて、就活生のパターンも把握しています。多少のコピペならバレないという根拠のない自信は捨てましょう。
ESでコピペを上手く活用する方法
表現や言い回しを変える
ESをコピペすることは基本的にはNGですが、コピペを上手く活用してオリジナルの文章を作成する方法もあります。
コピペした文章を一言一句そのままESに記載するのはご法度ですが、文章の語尾を変えたり、自分が使い慣れている言葉に置き換えたり、一部分のみを参考にしたりすることでオリジナルの文章になります。
コピペした文章に手を加えて、原形をとどめない自分らしい文章を作成していきましょう。
構成をそのまま真似する
ESの文章をコピペで使い回すのはNGですが、文章の「構成」を真似するのは問題ありません。
選考を突破したESと同じ構成で志望動機や自己PRを書くことで、理解しやすく、ボリュームも丁度よいESに仕上がります。
特に記入スペースが狭いESや文字数制限がある場合は、内定者がどのくらいの文字数で書いていたのかも参考にしましょう。
複数のESを参考にする
1人の内定者のESからコピペするのではなく、複数のESを参考にすると選考突破のヒントを得られるかもしれません。
それぞれのESから使えそうな文章や言い回しをピックアップすれば、採用担当者に響く魅力的な文章を導き出せるかもしれません。
内定者のESは学びが多いので、たくさん閲覧して、自己PR・志望動機の書き方のコツや、内定者の傾向を掴みましょう。
志望動機や自己PRが例文と似てしまったときの対処法
過去の経験談・インターンや説明会などの話を入れる
コピペをしていなくても、ネット上のESや例文と内容が似てしまうことはよくあります。
コピペを疑われたり、ありきたりな文章のままにならないようにするには、自分にしかない具体的なエピソードを盛り込むことが肝心です。
エピソードとは、学生時代の経験だけでなく、インターンや会社説明会、OBJECT・OG訪問に参加した時のことなど何でもOKです。
いつ、どこで、どんな経験をして、何を得たのか、具体的な名称や数字などの情報を盛り込み、オリジナリティのある文章に仕上げましょう。
自分が感じたことや考えたことを加える
志望動機や自己PRに盛り込んだ経験を通じて、自分は何を学んだのか、どんなことを考えたのかを付け加えましょう。
この一文に応募者の人柄や価値観が表れるので、採用担当者も注目しているポイントです。自分が感じたことを素直に表現すれば、面接で深掘りされても自信を持って答えられるはずです。
抽象的な表現は避け、できるだけ具体的で等身大の言葉でまとめましょう。
コピペチェッカーで確認する
「自分のESにオリジナリティがあるか気になる」「コピペと勘違いされないか心配」という人はコピペチェッカーを使うのがおすすめです。
ネット上には無料で使えるコピペチェッカーも多く存在し、文章を入力すれば類似した文章がないかすぐに確認してくれます。
もし、一致率の高い文章があった場合は、言い回しや単語を置き換えるなど修正したほうが無難です。
しかし、オリジナルで作った文章であれば、そっくりそのまま同じ文章が見つからない限り気にしすぎる必要はありません。
知人に添削してもらう
コピペチェッカー以外にも友人や知人に添削をしてもらうことで、「伝わりやすい文章か」「コピペのように見えないか」などを第三者の目で見て確認することができます。
特に就活を終えた先輩や就活中の友人、家族や身近な社会人の人などに頼むと、就活を経験した人の目線から添削してもらえるためより文章に磨きがかかるでしょう。
自分では気づかなかった誤字脱字にも気付いてもらえることもあるため、ESを出す前に最終チェックとして添削してもらうのも良いかもしれません。
書類選考を突破できるESの書き方
企業の求める人物像に当てはめて書く
書類選考を突破するには、企業の求める人物像と自分が合致していることを、志望動機や自己PRでアピールするのが効果的です。
企業がどのような人材を採用したいと考えていて、自分のどんな強みが当てはまるのかを考えてみましょう。
企業によっては求める人物像やスキルを明示しているところもありますが、見当たらない場合は企業理念から汲み取ったり、説明会や先輩社員から聞くなどして情報を掴んでおく必要があります。
構成を意識して書く
ESの志望動機や自己PRは「結論から書く」のが基本です。
結論の次に、「結論の裏付けとなる理由」、「具体例」を書き、最後は「強みをどう活かすか」や「入社後の目標」を述べて締めるのが王道の構成となります。
結論があやふやだったり、余分な情報が多すぎて文章の軸がぶれてしまうと、何が言いたいのかわからないESになってしまいます。
内定者のESの構成も参考にしながら、論理的な文章で採用担当者を納得させましょう。
使い回ししない
選考を突破できないESの特徴の1つに、志望動機や自己PRで「会社を入れ変えても違和感がない」という点があります。
採用担当者が知りたいのは、たくさんの同業他社の中で「なぜうちなのか?」という理由です。志望企業でなければならない理由を明確にして、志望動機や自己PRに盛り込みましょう。
どの企業でも話が通じそうなありきたりな文章では、採用担当者を納得させることはできません。
ESはコピペだけでなく、使い回しもすぐバレるので、1社1社丁寧に作成しましょう。
志望動機・自己PRが思いつかないときの対処法
自己分析を見直す
ESに書く内容が思いつかない時は自己分析を見直したり、深掘りをすることがおすすめです。
自己分析をする際、過去の経験を幼少期から時系列で振り返ることで、使えそうなエピソードや自分の強みが浮き彫りになることがあります。アルバイト経験や部活動、学業、課外活動など様々な出来事に焦点をあてて考えるようにしましょう
自分らしさがアピールできれば、特別な経験でなくても問題ありません。
始めから完璧なESを書こうとせず、まずはじっくりと自己分析を行い、深掘りをすることでより具体的で説得力のある志望動機や自己PRを書くことができるでしょう。
業界・企業研究を徹底する
ESが上手くまとまらないときは、業界・企業研究が不十分かもしれません。
志望企業が注力している事業や将来のビジョン、社風などを理解しておかないと、どこの企業にも使い回しできそうな無難なESになってしまいます。
自己分析と並んで、業界・企業研究は就職活動の基本です。より内容の濃いESを作成するためにも、業界・企業研究はじっくり行いましょう。
【ESメーカー】を使う
アピールしたい強みやエピソードは見つかったけど、上手く言語化できないという人は、ESメーカーなどAIによるES作成サービスを活用するのもおすすめです。
ESメーカーは、どんな文章を作成したいのか【質問】に入力し、【文字数】と【キーワード】の3つを入力するだけで、簡単に志望動機や自己PRを作成できます。
出来上がった文章を手直ししてブラッシュアップすれば、オリジナルの文章としてESに記載することができます。
ES作成に時間をかけられない人、文章づくりに苦戦している人は一度使ってみることをおすすめします。
【ChatGPT】を使う
ESメーカーと同じように、ChatGPTでも簡単に志望動機や自己PRを作成することができます。ただし、まだ精度はそれほど高くないので、不自然な言い回しも散見されます。
そのため、ChatGPTで生成した文章をそのままESに記載すると、「AIで作成したものをそのまま貼り付けた」と思われてしまうかもしれません。
AIで作成した文章はコピペチェッカーなどに引っかかる可能性は低いですが、自分ではなく他人が作った文章であることに違いありません。
自分の言いたいことがきちんと伝わる文章になっているか、必ず見直しをしてからESに記載しましょう。
ESは自分の言葉で思いを伝えよう!
ESをコピペするのは簡単ですが、バレると企業との信頼関係も一瞬にして崩れてしまいます。せっかく能力やスキルがあっても、コピペが発覚した時点で即刻不採用になってしまうでしょう。
コピペしたESでは応募者本人の人柄や熱意は伝わりにくく、採用担当者に違和感を与える可能性が高いです。
一方、自分の言葉で作ったESは、応募者のやる気や個性が伝わり、採用担当者の記憶に残りやすくなります。
ESは採用担当者が最初に目にする書類であり、応募者の第一印象に繋がる大切なものです。
悔いのない就職活動にするためにも、自分の言葉で企業への想いを伝えましょう。
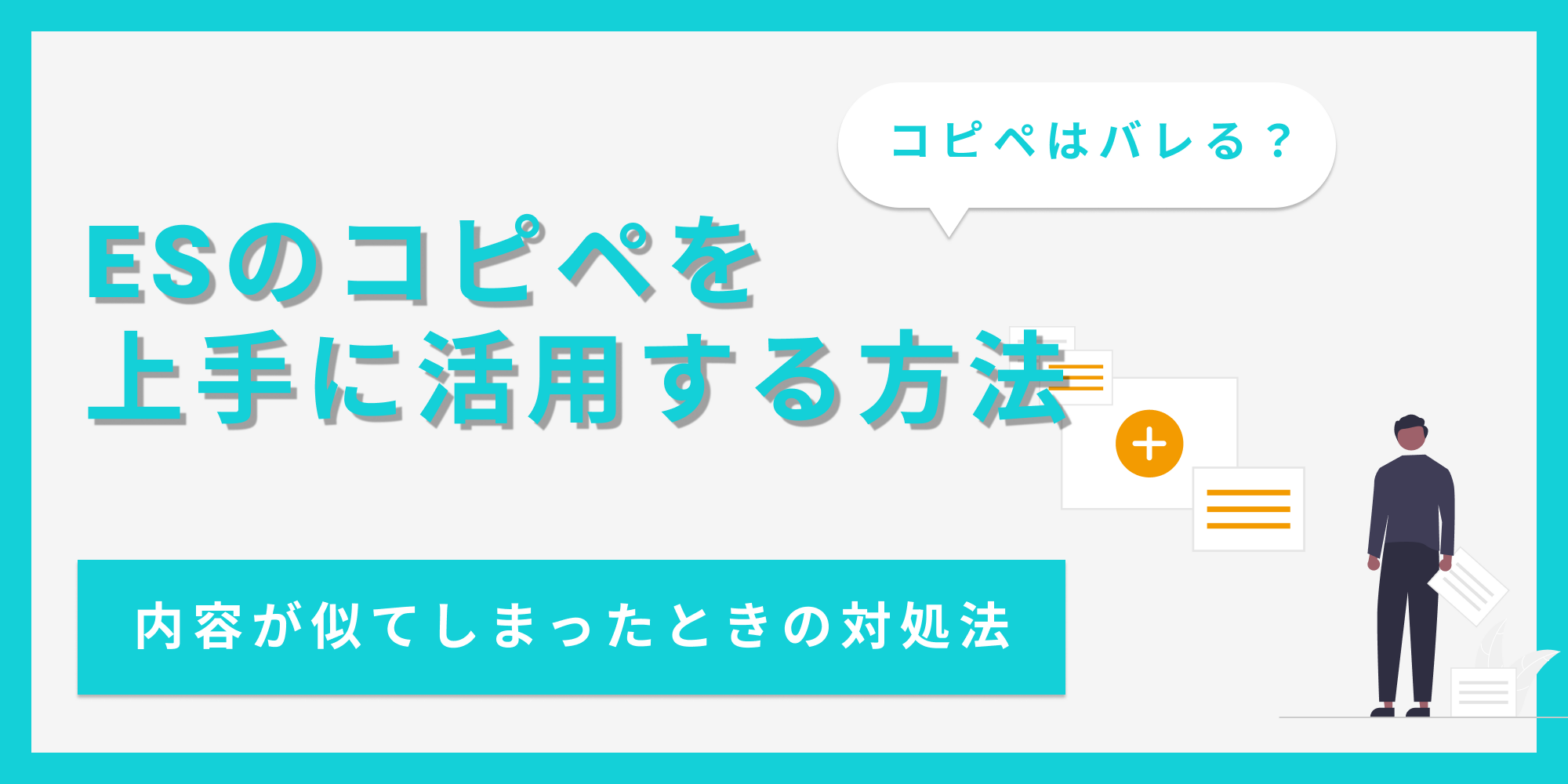



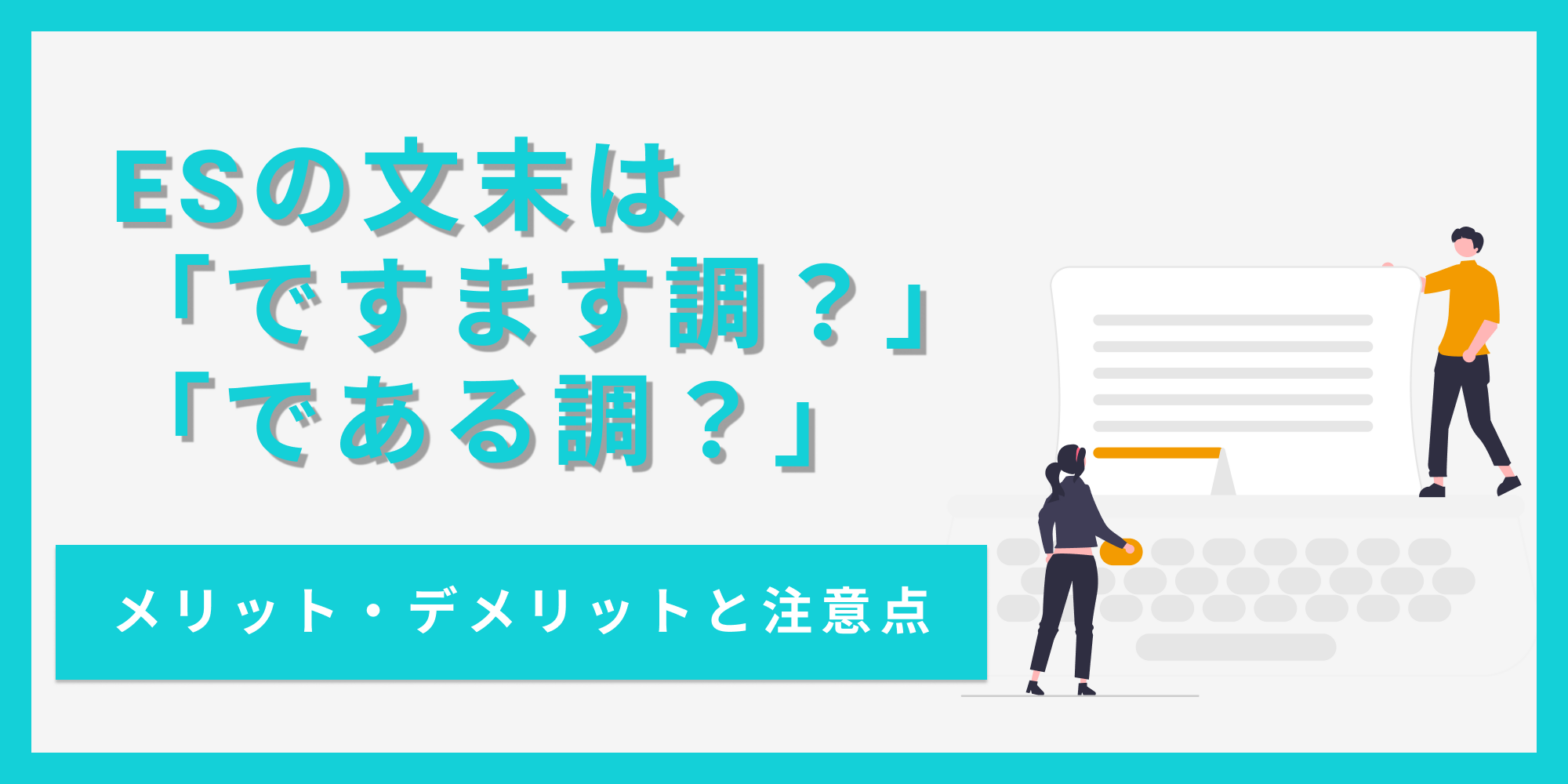



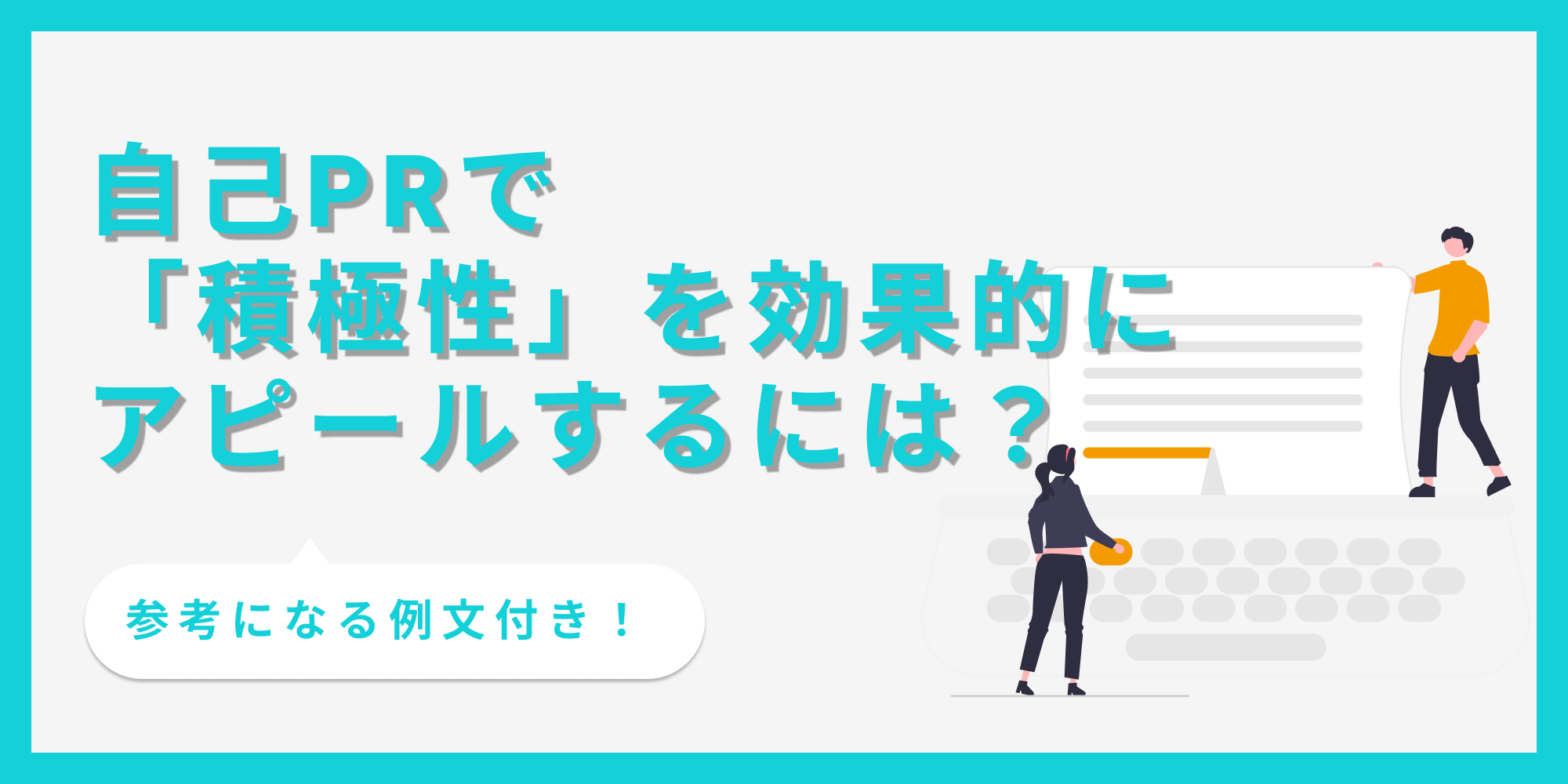


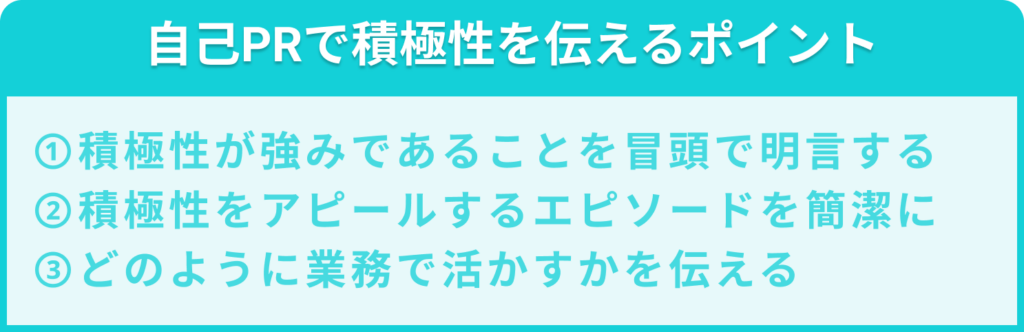





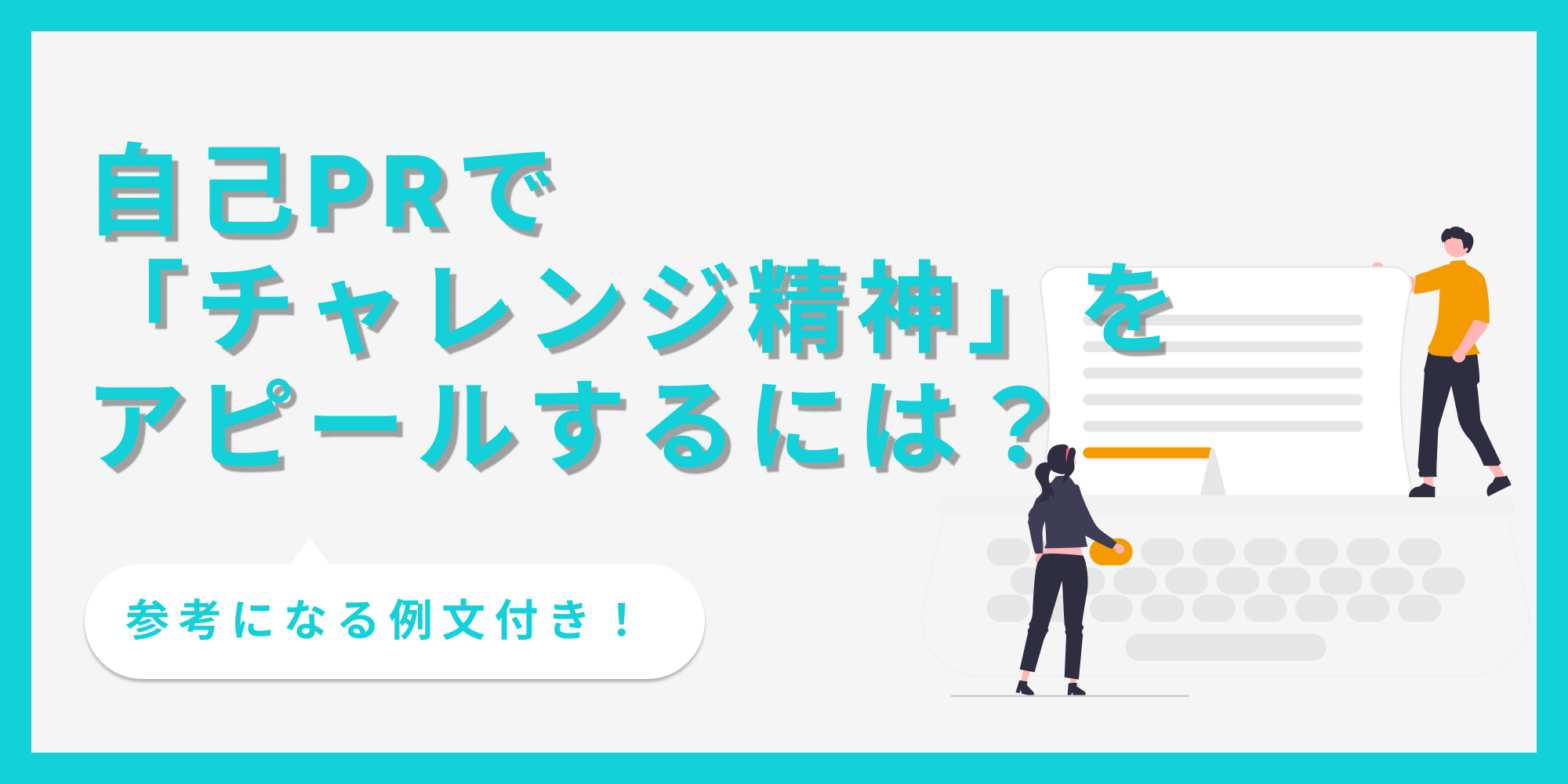
自己PR-チャレンジ精神-1024x377.png)