金融業界には、銀行や証券会社、保険会社など多くの業種が含まれています。まずは正しく金融業界を理解し、自分が金融業界の中でもどの業種を目指すのか、どのように貢献していきたいのかを考えましょう。
必ず企業ごとに適した志望動機を考えることが大切です。また、具体的なエピソードを盛り込むことで信憑性が高まり、他の志望者と差別化することができます。十分に業界研究・企業研究を行い、自分ならではの志望動機を作っていきましょう。
本記事では、例文とともに金融業界の役割、主な業種・職種、志望動機を書くときのコツを解説します。
金融業界の役割
資金を必要としている人に資金を融通することが金融業界の主な役割です。金融サービスの提供によって、起業の支援や事業の拡大などに貢献しています。
お金の貸付以外に、株式や債券といった金融商品の販売、保険の提供なども金融業界の事業に該当します。クレジットカード会社や資産運用会社も金融業界に属する業種です。
お金は人々の豊かで安心な暮らしに欠かせません。金融業界は人々の生活に密接に関わる業界だといえるでしょう。
金融業界の事業
銀行
金融業界の代表的な事業に銀行が挙げられます。個人や企業から集めた預金を、他の個人や企業に貸し付けることが主な仕事です。個人の資産維持・運用や住宅ローンの相談を受けて金融商品を提供するリテール業務も銀行業務のひとつです。
貸付の金利以外に、債権や株式の取引でも利益を生み出します。生み出した利益の一部を投資家や預金者に利息として還元します。
銀行の種類は主に、メガバンク、地方銀行、信用金庫、信託銀行、ネット銀行の5つです。
証券会社
顧客が株式や債券を売買する際に窓口となるのが証券会社です。
株式や債券の売買注文を証券取引所に伝えて成立させるブローカー業務、証券会社自身が株式や債券の売買をして利益を得るディーラー業務が証券会社の主な業務です。
顧客の企業が発行した株式を買い取って投資家に販売するアンダーライティング業務、株式を一時的に預かって投資家に販売するセリング業務もあります。
近年、証券会社の多くはオンライン取引のサービス向上に注力しています。
保険会社
保険会社の主な業務は、加入者から保険料を集め、病気や怪我、損害で困っている加入者に保険金を支払うことです。保険会社は、多くの人からお金を集めて、困っている人にお金を融通することから、金融業界に該当します。
集めた保険料で株式や債券の取引をすることも保険会社の業務のひとつです。株式や債券の取引で得た利益の一部は、配当として保険加入者に還元されます。
保険会社を大別すると、医療保険や入院保険といった生命保険会社、自動車保険や海外旅行保険といった損害保険会社の2種類です。
クレジットカード会社
クレジットカード会社は、顧客の飲食代やショッピング費用といった取引の金額を一時的に支払うことで手数料を得ます。
クレジットカード会社は、大きく分けると、国際ブランド、クレジットカード発行会社、加盟店管理会社の3種類です。
国際ブランドは、世界的に利用できる決済サービスを提供する会社です。VISAやMastercardなどが該当します。
入会手続きや審査などの会員管理を実施し、カードを実際に発行する会社がクレジットカード会社です。加盟店管理会社は、クレジットカード加盟店の新規開拓・管理を担う会社です。
資産運用会社
資産運用会社(アセットマネジメント会社)の仕事は、顧客から預かった資産を用いて株式や債券の取引をし、資産を増やす投資信託業務です。投資家に対してアドバイスをする投資顧問業務もあります。プロの投資家といえるでしょう。
証券会社が株式や債券を「売る」ために様々な調査・分析をするのに対し、資産運用会社は「買う」ために調査・分析をすることが一般的です。
企業によって目指す取引がローリスク・ローリターンなのかハイリスク・ハイリターンなのかが異なり、社風も異なります。
政府系金融機関
政府系金融機関は、経済発展や国民生活の安定といった政策を実現するために、特殊法人として設立された金融機関です。出資金の多くまたは全額を政府が出資しています。
民間の金融機関が貸付を避ける傾向にある、教育ローンや地方創生などへの融資をしています。
2024年2月現在、日本にある政府系金融機関は以下の5つです。
- 株式会社日本政策金融公庫
- 株式会社国際協力銀行
- 沖縄振興開発金融公庫
- 株式会社日本政策投資銀行
- 株式会社商工組合中央金庫
金融業界の職種
| 営業 | 金融商品を顧客に提案する職種 |
| ファイナンシャルプランナー | 個人の生命保険や住宅ローンなどの資産運用にアドバイスをする職種 |
| ファンドマネージャー | 投資信託運用の指揮をする専門家 |
| 証券アナリスト | 金融に関わる情報を収集し分析する職種 |
| アクチュアリー | 保険料率や支払保険額を算定する職種 |
| 保険外交員 | 保険契約の勧誘、代理、サポートをする職種 |
| プライベートバンカー | 主に企業の経営者に、事業や資産の継承に関わる金融サービスを提案する職種 |
| トレーダー | 顧客の指示で証券の売買取引をする職種 |
| ディーラー | 金融機関が集めた資金を用いて自己判断で証券の売買取引をする職種 |
| クオンツ | 数理技術で金融商品の価値を分析する職種 |
営業は主に、個人向けと法人向けに分けられます。個人向け営業では人の人生に、法人向け営業では企業の経営に深く関わります。
日商簿記2級を取得していれば、金融業界のあらゆる職種で有利に働くでしょう。ファイナンシャルプランナーを目指している人には、2級FP(ファイナンシャル・プランニング)技能士の取得をおすすめします。また、正式なアクチュアリーにみなされるためには、公益社団法人アクチュアリー会の資格試験に合格し正会員になることが必要です。
上記の表以外にも、総務、労務、人事といったバックオフィスと呼ばれる職種もあります。
金融業界の志望動機で書くべき内容
なぜ金融業界を志望するのか
金融業界を志望する理由を十分に述べます。金融業界で活躍したい、人々の暮らしに欠かせない金融業界に貢献したいといった強い想いをアピールすることが大切です。
できる限り具体的なエピソードを志望動機に盛り込みましょう。具体性に欠けると、金融業界で働きたいという想いが採用担当者に十分に伝わりません。自分の体験や感じたことをもとにして述べることで、金融業界を志望する理由の説得力が増します。独自のエピソードを述べることで他の志望者との差別化も図ることができるので、自分ならではの理由を考えましょう。
なぜ応募先を志望するのか
金融業界の中でも、なぜ応募先を志望するのかを説明します。
応募先が求める人物像に合わせて志望理由を述べましょう。前述したように、金融業界には様々な業種があります。同じ業種でも、企業によって社風が大きく異なるため、求める人物像も異なります。
求める人物像に合わせて志望理由を述べないと、あなたが優秀で魅力的な人物であると評価されても、自社には合わないだろうとみなされ、不採用になるかもしれません。
応募先の公式サイト、募集要項、企業説明会などで、応募先が求める人物像を十分に把握することが大切です。
就きたい職種は何か
志望先で就きたい職種を述べましょう。前述したように、金融業界には多くの職種があります。業種だけでなく職種によっても求められる能力や経験が異なります。
やはり志望先の公式サイト、募集要項、企業説明会などで調べ、志望先が求める人物像を十分に把握したうえで自分のアピールポイントを述べることが大切です。
例えば、営業職や保険外交員を志望する場合は、コミュニケーション能力や提案力をアピールしましょう。ファイナンシャルプランナーやファンドマネージャーを志望する場合は、コミュニケーション能力や提案力に加えて情報収集力や勉強を継続する姿勢を伝えることをおすすめします。
達成したい目標は何か
金融業界で達成したい目標を述べることも大切です。ただ金融業界で働きたい、活躍したいとだけ伝えても、達成したい目標を述べないと信憑性に欠け、熱意が伝わりません。金融業界で達成したい目標を具体的に述べましょう。
入社前から目標を定めることは難しいと感じている人は、可能であれば金融業界の先輩社員から話を伺ってみましょう。実際に働く人の想いや悩みを聞くことで、自分が金融業界で働く姿が想像できるでしょう。
金融業界の志望動機の例文
例文①
私は、資産運用サービスの提供によってひとりでも多くの人々の生活を支えたいと思い金融業界を志望しています。
私は現在、高齢者支援のボランティア活動に関わっています。高齢者の中には、資産に余裕がなく望む医療や介護を受けられない人もいれば、コツコツと積み立てた資産によって十分な医療や介護を受けられる人もいます。若い頃には保険の重要性を知らず、後悔している人も多くいました。この経験から、資産運用の大切さを実感しました。
日本を代表する銀行としてグローバル展開にも注力し、多くの人々の生活を支える役割を果たしている貴行に魅力を感じて志望しました。ファイナンシャルプランナーとして一人ひとりに適した資産運用サービスを提案し続けたいと考えています。(350字以内)
高齢者支援のボランティア活動での体験をもとにした、メガバンクへの志望動機例文です。独自のエピソードが述べられているため、他の志望者と差別化できます。
少子高齢化により、高齢者に金融サービスを提供する機会も増えるでしょう。ボランティアに取り組んでいるときに高齢者と適切なコミュニケーションをとった経験があれば伝えましょう。ファイナンシャルプランナーは、顧客と信頼関係を築き上げるために高いコミュニケーション能力が求められます。
例文②
私は、海外旅行保険の提供によって困っている人を助けたいという想いで貴社を志望しました。
私は、ひとりで海外旅行をした際に荷物の盗難に遭い、周囲に頼れる人がおらず途方に暮れていました。現地の人と可能な限りコミュニケーションをとりましたが、対処方法はわかりませんでした。
そこで、念のために加入していた海外旅行保険の会社に連絡したところ、対処方法を教えてもらえ、無事に帰国できました。帰国後も、盗難品の補償を十分に受け取れました。この経験から、いざというときに頼れる保険の大切さを学びました。
特に海外旅行保険サービスに注力している貴社で、損害サポートに従事し、困っている人をひとりでも多く助けたいと思っています。(350字以内)
自分が海外旅行で苦労した経験をもとにした、保険会社への志望動機例文です。他の志望者と被りにくい貴重なエピソードが具体的に述べられています。
海外旅行保険サービスに関わる仕事に就くのであれば、語学力や異文化理解が必要です。世界情勢の知識や情報を常に収集し続ける姿勢も求められます。アピールできる語学スキルや、文化や習慣の違う海外の人々とのコミュニケーション経験があれば伝えましょう。
例文③
私は、金融業界で多くの人の不安を解消したいと考えています。
周囲の友人と話していた際に、将来について漠然とした不安を抱えているという話になりました。老後の生活はどうなるのか、働いているときに病気になったらどうなるのかといった不安要素が多くありました。多くの人が同様の不安を感じていると思います。
これらの不安要素について調べるうちに、人々の不安を軽減する資産運用サービスを多く提供している貴社を知りました。
私は大学で流体力学のシミュレーションに取り組んでいます。身に付けたプログラミング知識やシミュレーション手法を活かし、貴社で投資戦略の分析に従事したいと考えています。
精度の高い分析手法を確立し、多くの人が抱える将来の不安を解消していきたいです。(350字以内)
自分が感じたこと・考えたことをもとにした志望動機例文です。将来の漠然とした不安は誰もが感じることであり、誰でも同じ内容を書けるかもしれません。しかし、独自の体験として述べることで志望する想いの説得力が増します。
近年、金融業界はIT化に注力しています。分析ツールの発展、オンライン取引をしたい顧客の増加、暗号資産の普及などが理由です。理系の学部に所属している人でも十分に活躍の機会があります。
例文④
私は、地元の産業を助けたいという想いで貴行を志望しました。
新型コロナウイルスの影響により、業績不振に陥った飲食店が私の地元に多くありました。多くの飲食店が困っている中で、地元を支える貴行が、融資や事業計画の相談によって地元の飲食店をサポートしていたことを知りました。貴行の尽力によって閉店を免れた飲食店も多くあると伺いました。地元は現在、新型コロナウイルス流行前の活気を取り戻しつつあります。
私は大学で経済学を専攻しており、日本全体の財政と地方財政の関連性について学んでいます。大学で学んだことを活かし、私の地元を支える代表的な銀行である貴行で営業職として活躍し、地元の産業に貢献し続けます。(300字以内)
地元の飲食店をサポートしている地方銀行への志望動機例文です。金融業界で地元に貢献したいという想いが具体的なエピソードによって述べられています。
応募先の魅力を述べるとともに、大学で経済学を学んでいるという自分の強みもアピールしています。入社したいという想いだけでなく、自分がどのようなスキルを持っているのか、どのように活躍するのかを伝えることが大切です。大学で学んだことでなくとも、コミュニケーション能力や継続する姿勢などの強みがあればアピールしましょう。
金融業界の志望動機を書くときのコツ
企業が求める人物像を把握する
企業が求める人物像を十分に把握した上で金融業界の志望動機を書くことが大切です。
前述したように、金融業界の業種や職種は多岐に渡ります。業種ごと、職種ごとだけでなく企業ごとにも求められるスキルや経験は異なります。
企業が求める人物像に合わせて自分の魅力をアピールしないと、優秀な人材だと評価されても採用につながらないかもしれません。
志望先の公式サイト、募集要項、企業説明会などで志望先が求める人物像を調べましょう。求める人物像に合わせて、志望先ごとに志望動機を一つひとつ作成することで、志望先に真剣さが伝わります。
ただし、企業が求める人物像に無理やり合わせる必要はありません。自分の体験や感じたことの中から、企業が求める人物像に合ったエピソードを選んで述べましょう。
入社後の目標やキャリアプランを述べる
金融業界で働きたい理由だけでなく入社後の目標やキャリアプランも述べましょう。目標やキャリアプランを述べることで、金融業界への想いの強さをアピールできます。目標やキャリアプランが具体的であれば、熱意とともに情報収集力も伝えられます。
前述したように、可能であれば金融業界で働く先輩社員の話を直接聞きましょう。目標やキャリアプランを具体的に考えられるようになります。他の志望者との差別化にもつながるでしょう。
根拠のある具体的なエピソードを盛り込む
金融業界の志望動機に根拠のある具体的なエピソードを盛り込むことも重要です。具体的なエピソードを述べることで、志望理由の信憑性が高まったり他の志望者と差別化することができます。十分に自己分析をして、金融業界を志望するに至った経験を洗い出しましょう。
さらに、後述する金融業界で求められるスキルを具体的に盛り込むと、自分をより魅力的にアピールできるでしょう。特にコミュニケーション能力はどんな業種・職種でも求められるので、エピソードをひとつは思い浮かべておくことをおすすめします。
金融業界に求められるスキル
コミュニケーション能力
コミュニケーション能力は、金融業界のあらゆる業種・職種で求められるスキルです。
顧客と円滑なコミュニケーションを図らないと、顧客に大切な資産を預けてもらえないでしょう。誠実にコミュニケーションをとって信頼関係を築き上げることが重要です。
顧客と直接関わらない職種でも、自分一人で成し遂げられる仕事はほとんどありません。大金を扱う以上、多くの人と協力して仕事を進める必要があります。
志望動機に盛り込まなくても、面接で問われた際に回答できるように、コミュニケーション能力を発揮したエピソードを少なくともひとつは準備しましょう。
継続する姿勢
金融業界では、金融に関する知識や情報を収集し続ける姿勢が求められます。
世界情勢によって日本の経済状況は大きく変化します。株式や債券、通貨の価値が急騰することもあれば暴落することもあるでしょう。金融業界の業績は経済状況に大きく左右されます。
各業界・企業の経営状況から世界各国の政策や気候まで、幅広く最新の知識や情報を身に付けなければなりません。
継続する姿勢をアピールできるエピソードがあれば、志望動機に盛り込みましょう。
柔軟性
初めての問題に直面しても慌てず適切に対応する柔軟性も、金融業界で働くうえで重要です。
前述したように、株式や債券、通貨の価値は、社会情勢によって大きく変わります。問題が起きたときに適切に速やかな対応をしないと、大きな損失が発生するかもしれません。どんな変化に直面しても、柔軟性を持って対応することが求められます。
問題が起きたときに柔軟な対応をして解決した経験があれば、志望動機に盛り込むことをおすすめします。

金融業界の魅力的な志望動機を作成しよう!
金融業界の役割、主な業種・職種、志望動機を書くときのコツを解説しました。
金融業界には多くの業種・職種があり、それぞれ求められるスキルや経験が異なります。業界研究・企業研究を十分にして、応募先ごとに適した志望動機を考えることが大切です。
具体的なエピソードを述べることで他の志望者と差別化できます。自己分析をして応募先への志望動機にふさわしいエピソードを見つけましょう。
ぜひ本記事を参考に、金融業界への志望動機を作成してみてください。






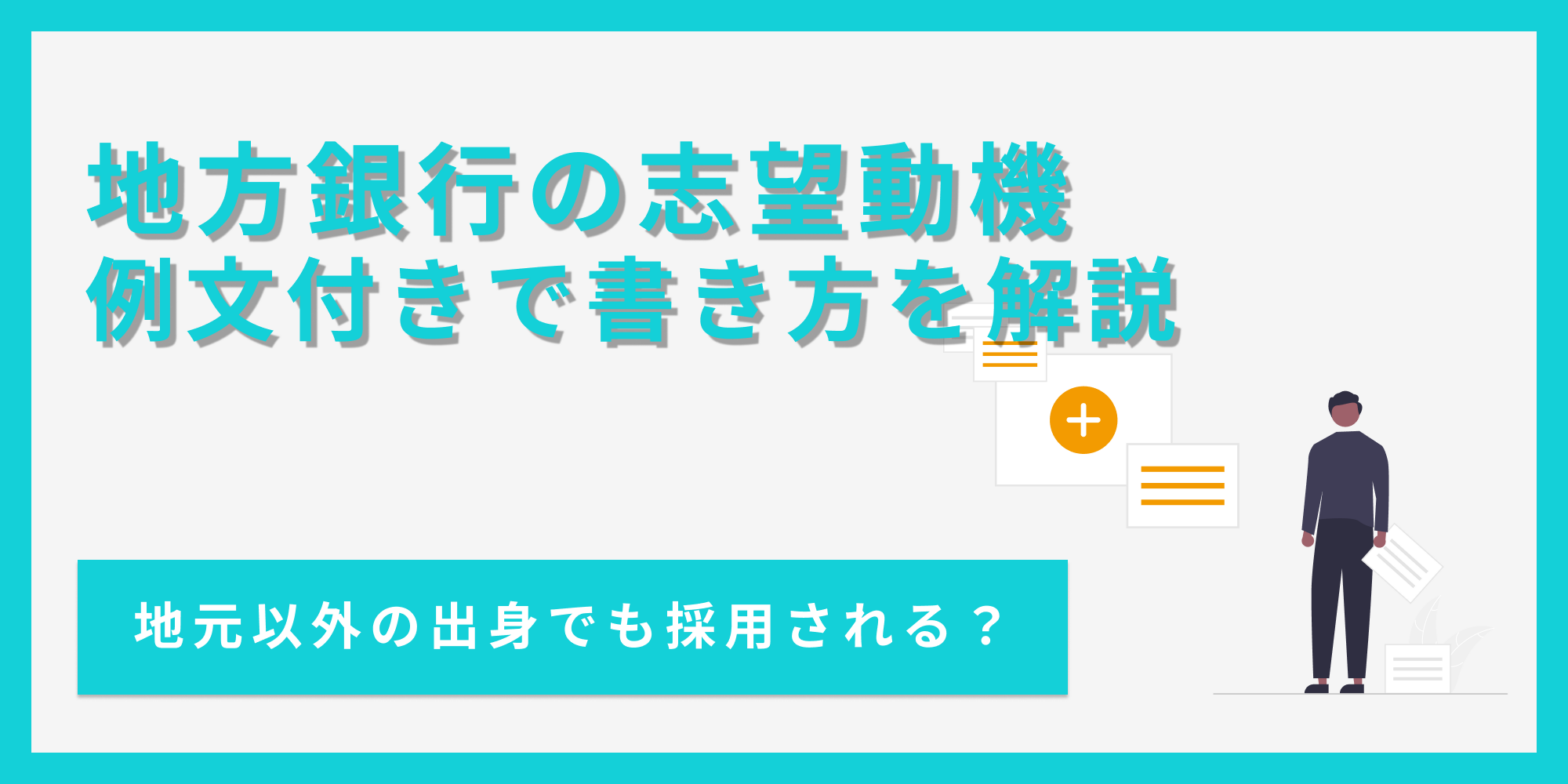



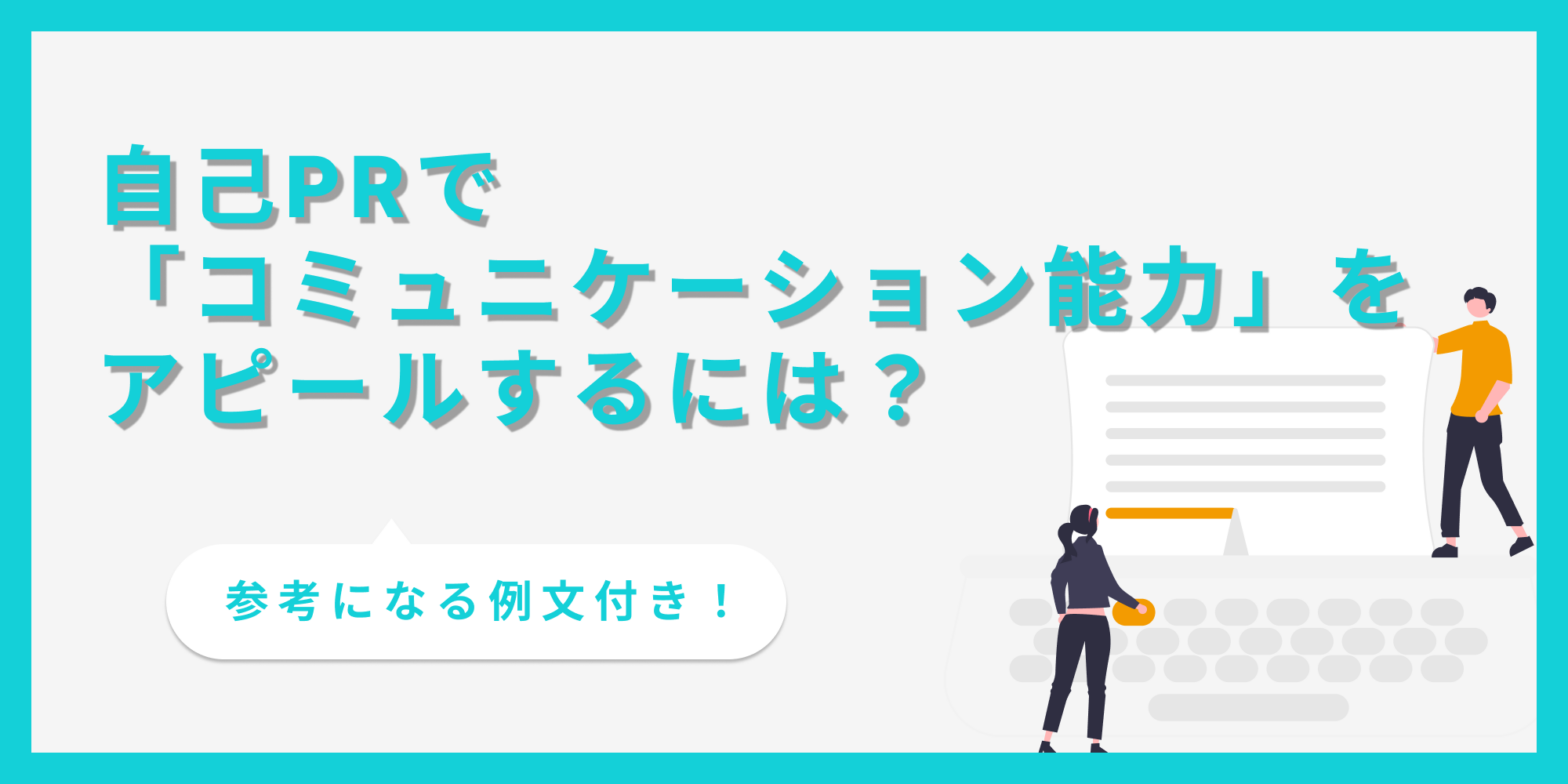



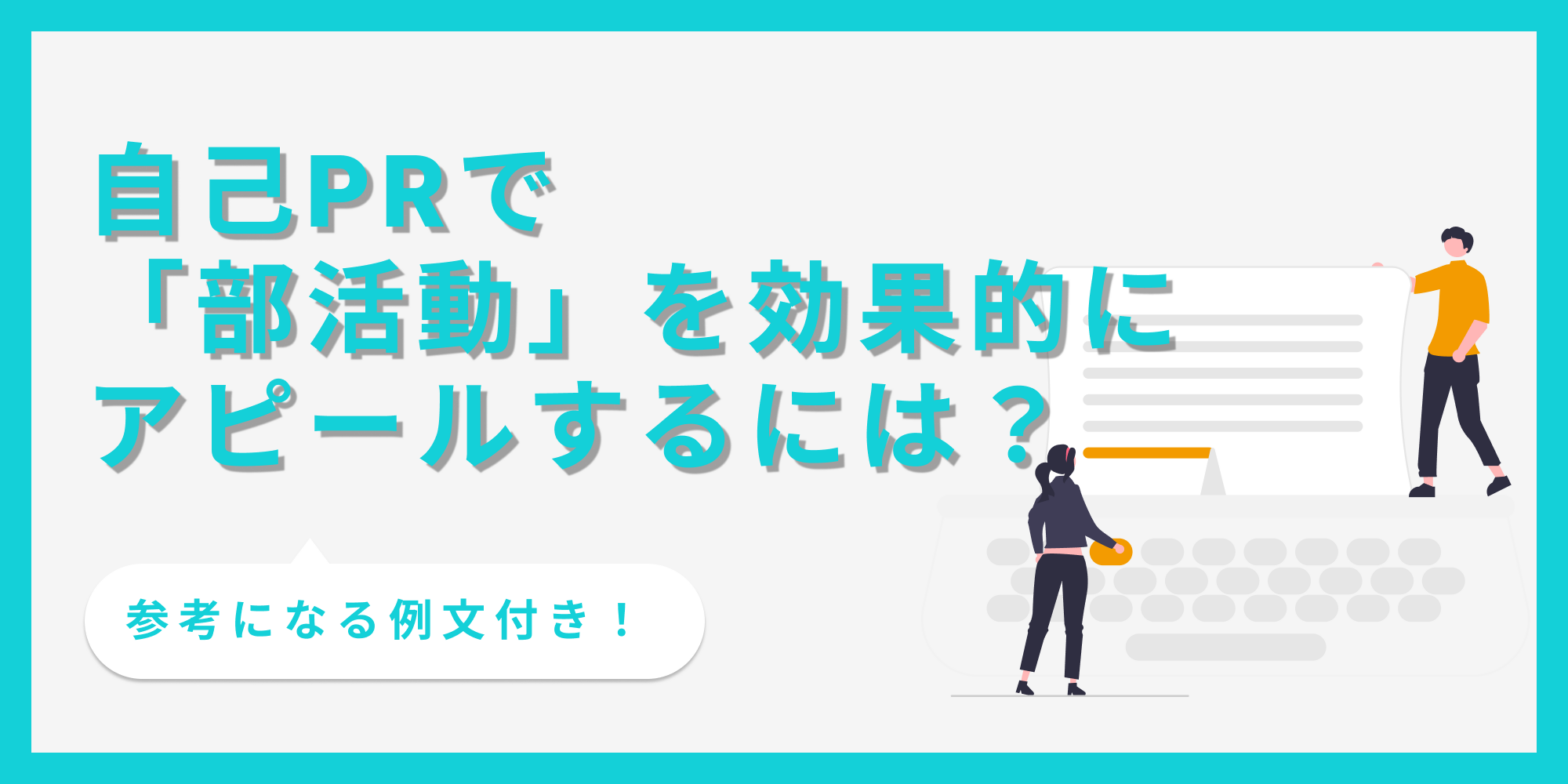




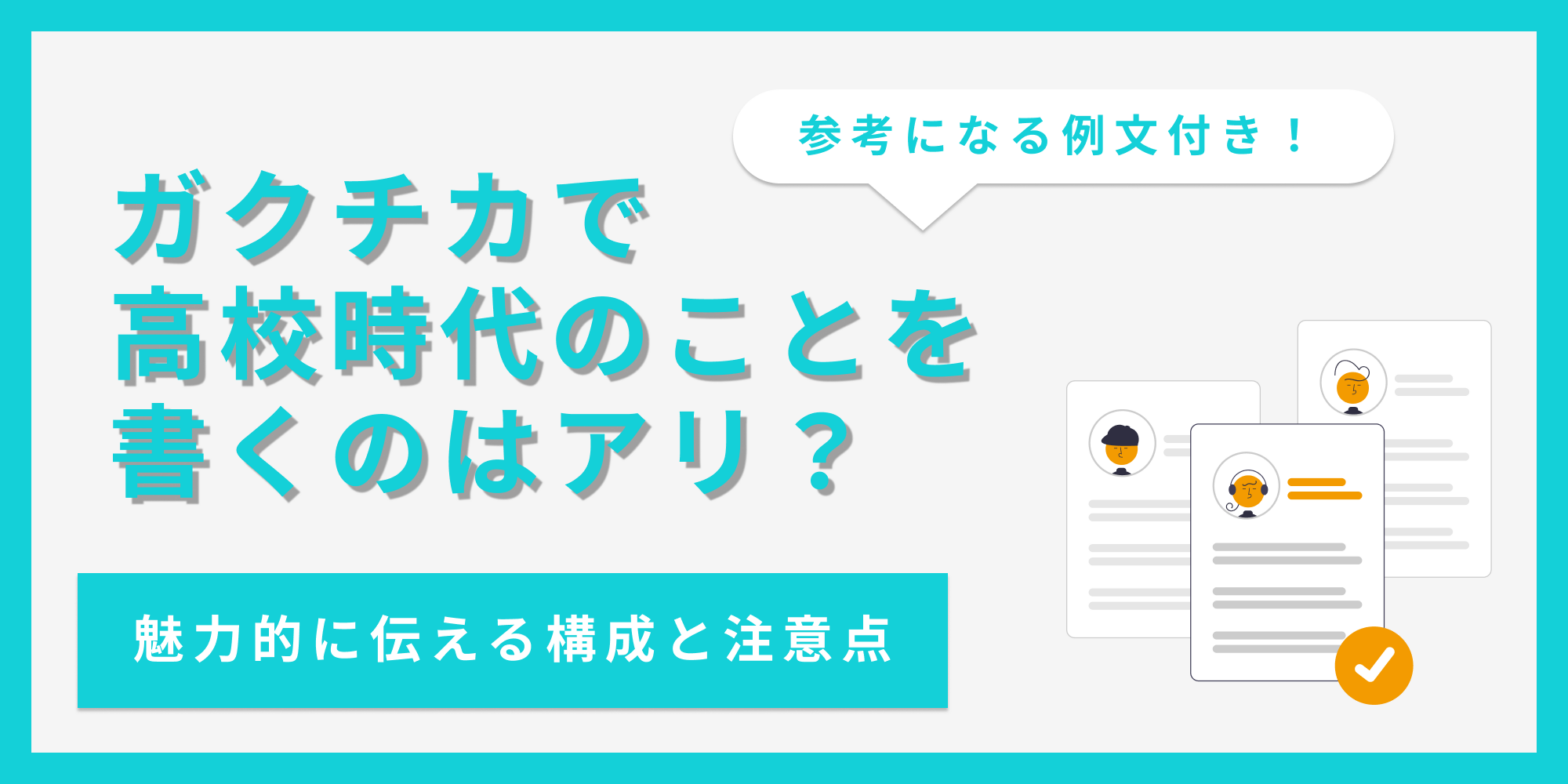

-1568x784.png)

-1568x784.png)





-1568x784.png)

-1568x784.png)


