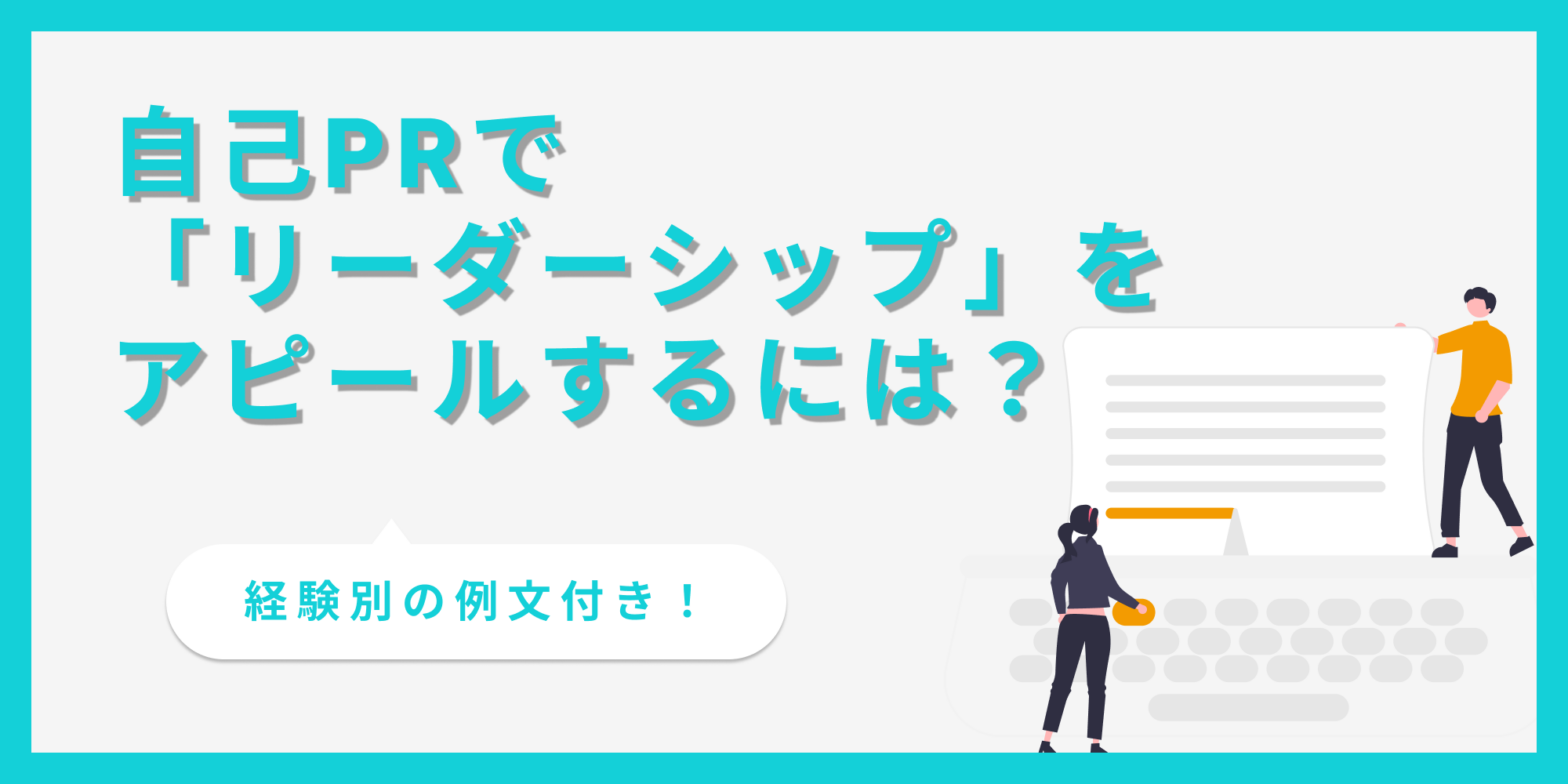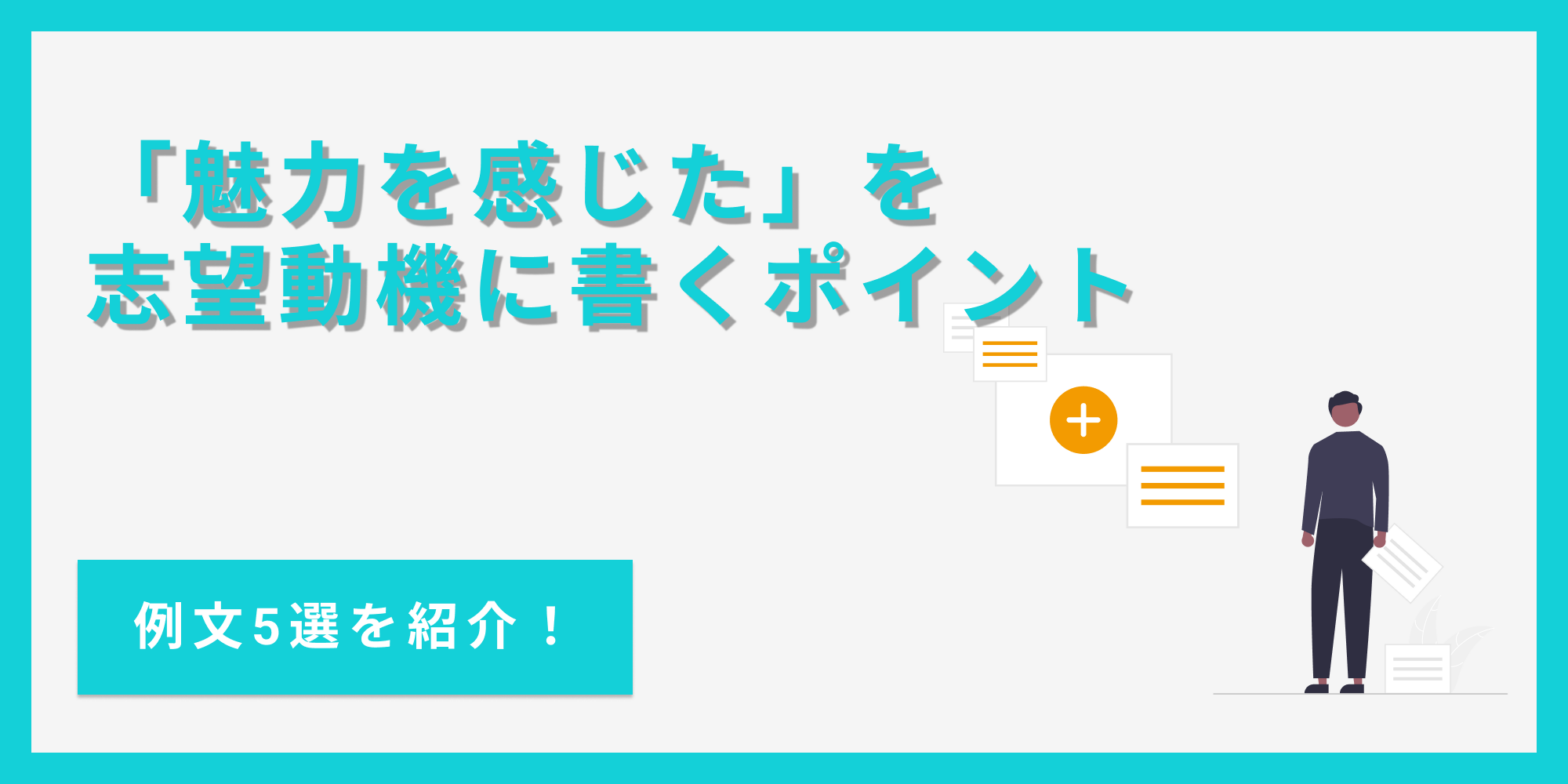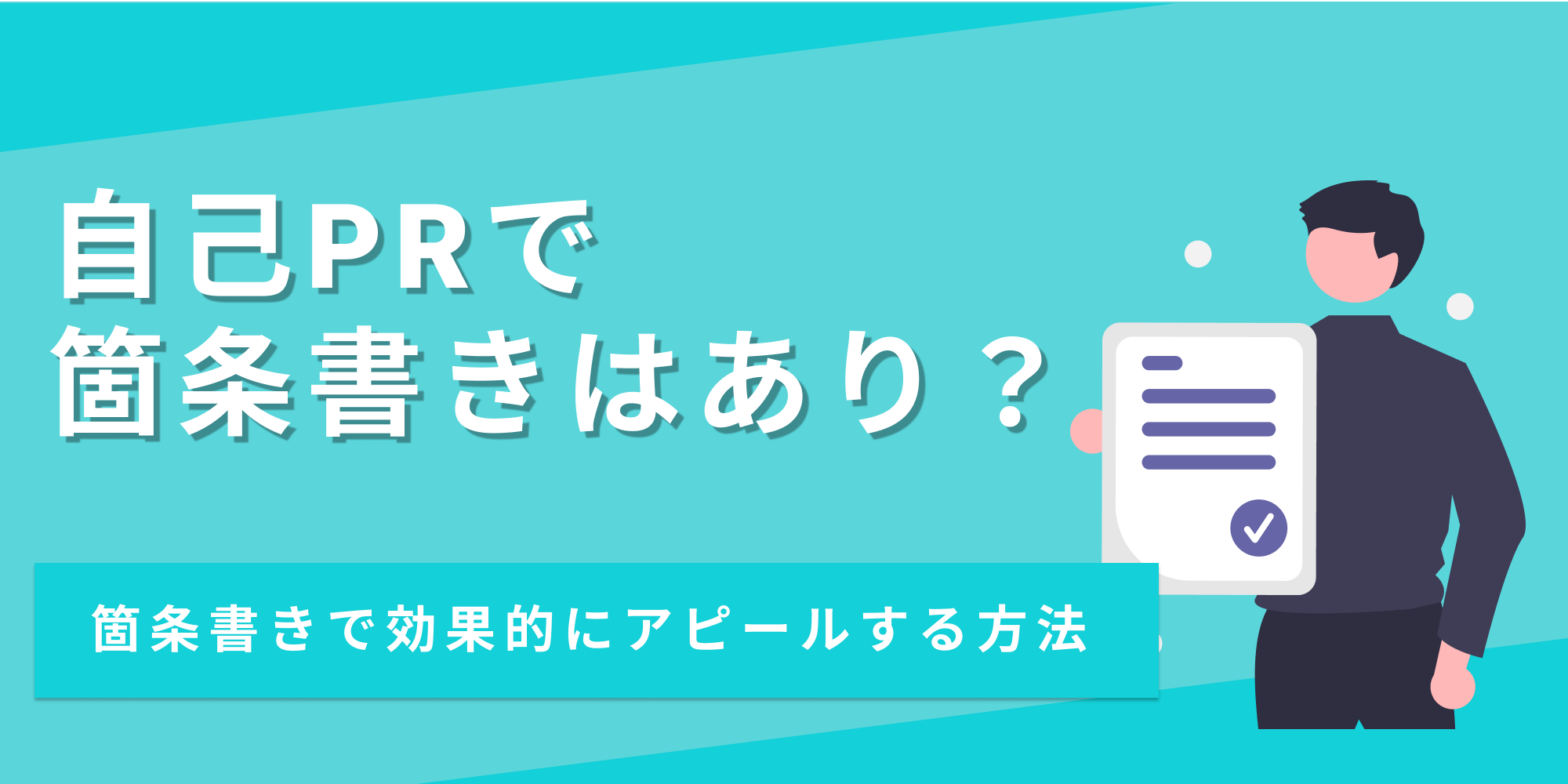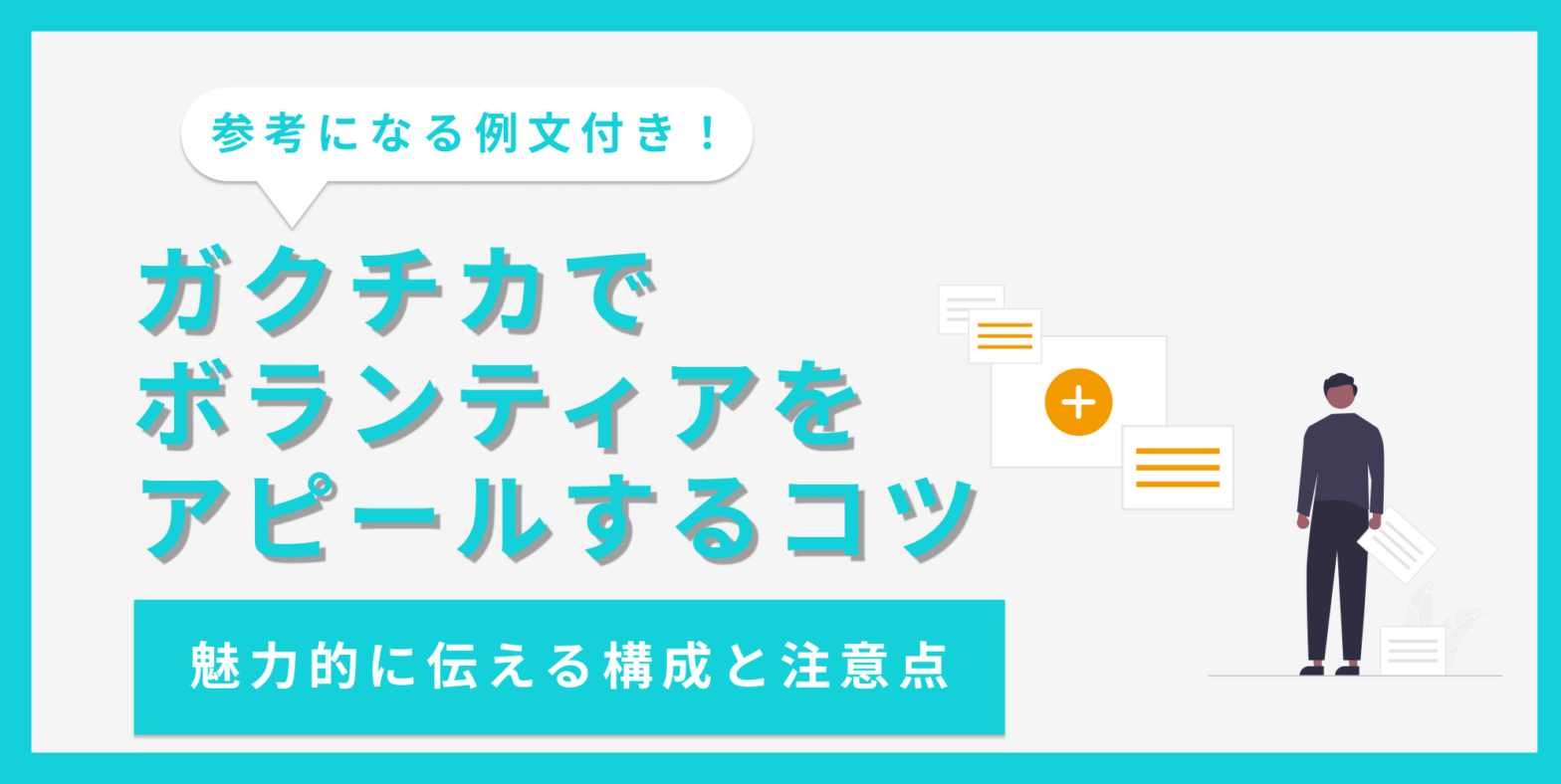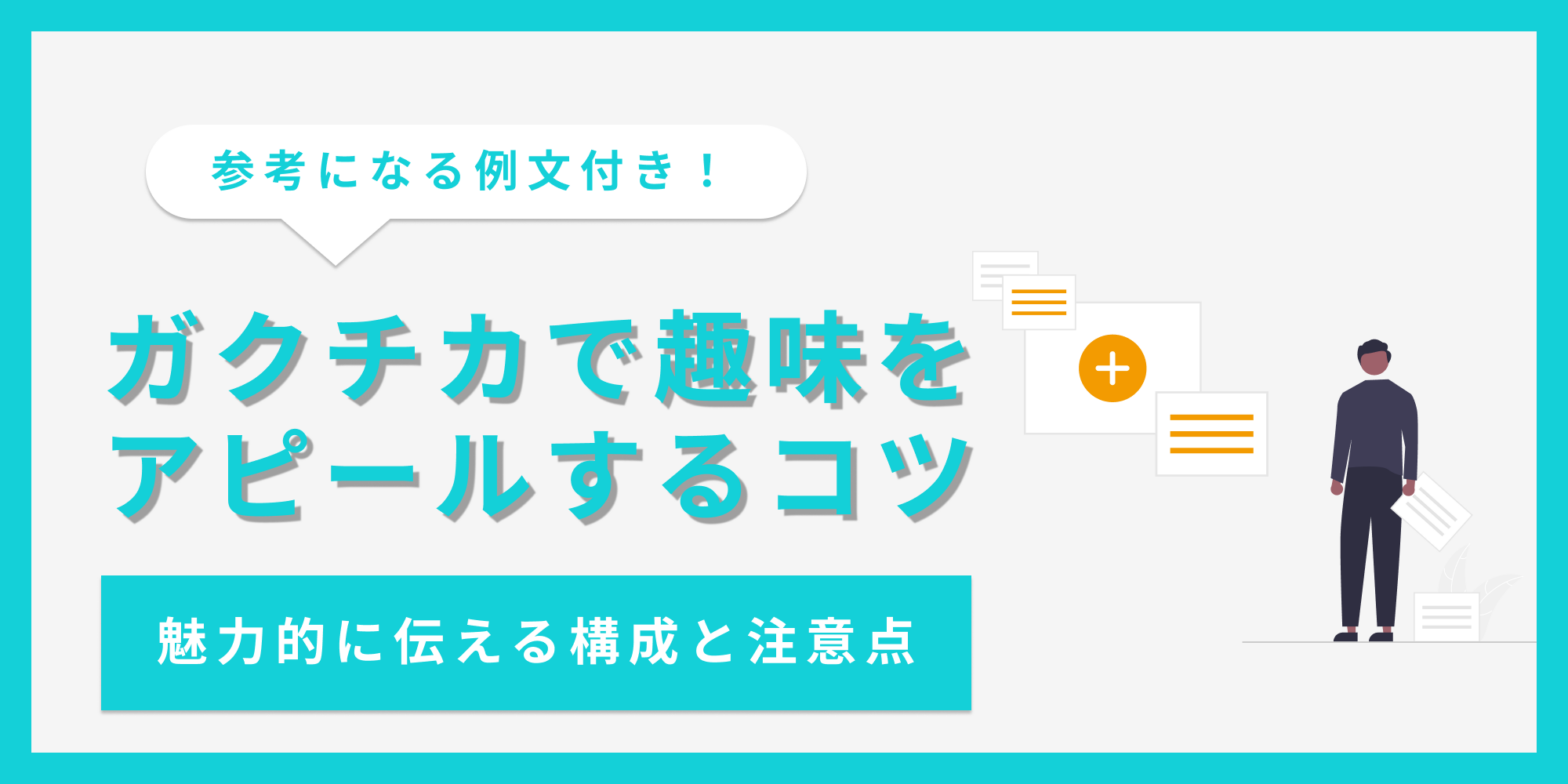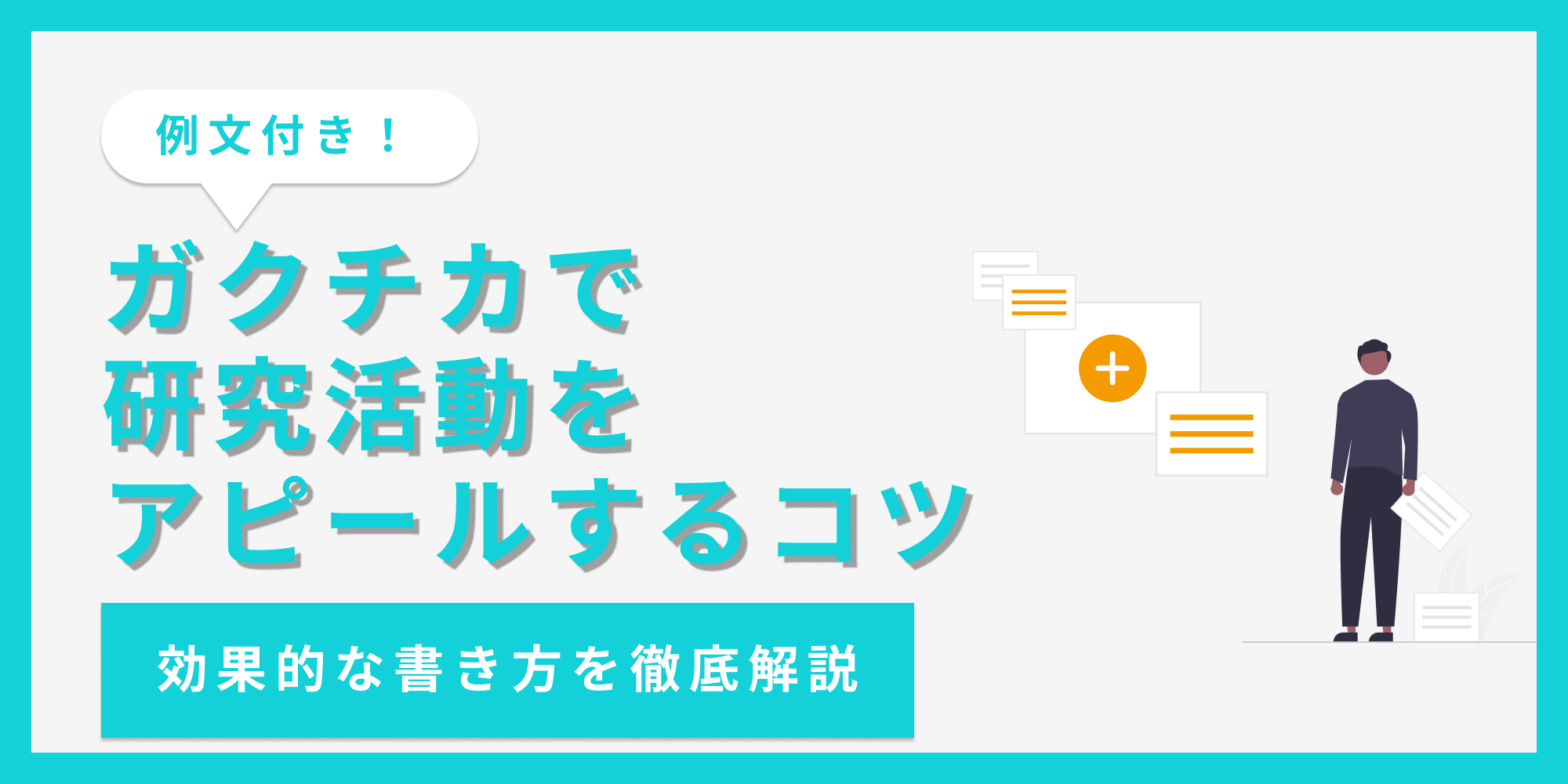アルバイトの応募でも、履歴書の提出を求められることは多いです。しかし、応募書類を書き慣れていない方の場合、効果的な自己PRが書けずに、自分の強みをうまく伝えられない可能性があります。
この記事では、自己PRの書き方の基本から、アルバイト用の自己PRとしておすすめの内容を、場合別・職種別の例文付きで解説していきます。
アルバイト用の履歴書でも自己PRを書かないのはNG!
アルバイト用の履歴書であっても、自己PRを書かないのは絶対に避けるべきです。しかし、これまでの職歴が無く、初めてのアルバイトになるという方にとっては、何をアピールするべきか迷うことがあります。
ほとんどのアルバイトは未経験に近い人を採用することになるため、採用担当者は志望者のやる気や人柄を重視していることが多いです。そのため、具体的に示せる能力がなかったとしても、内面的な部分をアピールすることが重要です。
また、優れた能力や経験を持っていても、履歴書からそのことが伝わらなければ意味がありません。アピールしておきたい強みはしっかりと明記し、少しでも採用の可能性を高められるように工夫しましょう。
アルバイト用の自己PRの基本的な書き方
最初に結論を書く
自己PRでは、最初に結論として「自分は何が強みなのか」を明示しておくのが基本です。理由から結論という順番で書き始めると、最後の結論を読むまで何がポイントなのかがわからず、結果的に魅力の伝わりにくい自己PRになってしまいます。
また、文字数に余裕がある場合には、最初に簡潔な強みを述べ、最後に理由を踏まえた詳細な強みを述べることで、印象が強くなる効果があります。
文字数は200字程度
アルバイト用の自己PRでは、それほど長々と書くことは求められていません。最低で100字程度、多くとも250字程度までに収まるようにまとめることを意識しましょう。
ただし、履歴書によっては自己PRと志望動機が1つの枠になっていることがあります。その場合は、自己PRと志望動機の合計で300~400字程度になるように調整しましょう。
人柄の伝わるエピソードを取り上げる
アルバイトの自己PRでは、人柄や性格のアピールが有効となります。特に、「根気強い」や「積極性がある」といった、業務に貢献できるような性格は高く評価されます。
自分の性格は、直接的に書くだけではなく、それを裏付けるようなエピソードを踏まえて述べると良いでしょう。これまでの経験を振り返り、アピールしたい性格が発揮されたのはどんな時だったのかを明確にすることで、説得力が高まります。
ここで取り上げるエピソードは、基本的にどんなものでも問題ありませんが、あまりにも古すぎるものは説得力に欠けると判断されかねません。例えば、高校生のアルバイト応募の際に、小学生の時のエピソードを取り上げても、良い印象は与えにくいでしょう。
内容に具体性を持たせる
自己PRでアピールする強みは、なるべく具体性を持たせるようにしましょう。広い場面で役立てることをアピールしようとして、「どんな業務にも精一杯努めます」といった書き方をしてしまうと、具体的にどの場面で強みが発揮されるのかが伝わりません。
また、取り上げるエピソードも時期や場面などをある程度絞り込み、「〇年間の部活動で〇〇を培った」のような漠然とした記載は避けるようにしましょう。
自己PRでは、万能な強みではなく、自信を持って伝えられるような少しの強みを伝えられれば十分です。曖昧な強みよりも、自分の正確な強みをアピールすることが重要となります。
根拠のあるアピールを心がける
自己PRで述べる強みには、根拠が必要です。特に能力面でのアピールは、説得力のある根拠を示すことが求められます。
根拠や経験が無いにもかかわらず、「〇〇をすることができます」というアピールをしても、採用には繋がりません。できることをアピールしたいのであれば、それを裏付けるエピソードを選んで記載するようにしましょう。
もし、アピールしたいことについての根拠が薄くなってしまうようであれば、「〇〇できるように努力したいと考えています」といった意欲のアピールに切り替えることがおすすめです。意欲に強い根拠は必要ないため、比較的自由に自己PRを述べられます。
応募先に合った内容にする
自己PRの内容は、応募先が求める人物像と合致しているかどうかを確かめながら作成しましょう。アルバイトは応募先によって、合う強みや人柄が分かれます。自分に合った求人を見極めるのはもちろんですが、応募書類も応募先に合った内容で書くことが重要です。
例えば、コンビニのように長時間営業の店舗の場合、安定して長時間働ける人が求められる傾向にあります。一方、引っ越しのような体力勝負の仕事では、動くべき場面でてきぱきと作業をこなす瞬発力が求められるでしょう。
複数の強みがあっても、それらを全て列挙するのではなく、より応募先に合った強みを中心に自己PRを組み立てることで、有用な印象を与えられます。
アルバイト用の自己PRにおすすめの内容
自分が長所だと考えていること
自己PRはあくまで自己申告であり、最終的にそれが正しいかどうかを判断するのは採用担当者です。そのため、自分の長所だと思う点は自信を持ってはっきりとアピールするようにしましょう。
「私の強みは〇〇だと考えています」といった表現は、自信がないように見えるため避けるべきです。特に、強みを伝えるのは基本的に冒頭となるため、断定する形で強みを言い切ることで、続く理由の部分の説得力も高まります。
学校の部活動での経験
高校生や大学生の場合、エピソードとして取り上げられる経験の多くは学校生活についてのものになるでしょう。強みが活きた経験であれば、仕事とは関係のない場面でも問題ありません。
ただし、「友人との会話」や「授業中」など、誰もが経験するような日常的な場面についてのエピソードは、強いアピールには繋げにくいです。
そのため、部活動やクラブ活動における、特定の場面についてのエピソードがおすすめです。試合に向けた練習や試合本番などのエピソードは個性が強く表れるため、他の応募者との差別化を図ることもできます。
これまでのアルバイト経験
これまでにアルバイトをした経験がある場合は、積極的にアピールしましょう。もし、応募先と関連の薄いアルバイト経験だったとしても、仕事に携わったことがあるというだけで十分な評価点になります。
応募先と関連のあるアルバイト経験があれば、業務内容を細かく記載し、自分がどのような業務に携われるのかを明記しましょう。
一方で、応募先と関連の薄いアルバイト経験しかない場合には、業務内容を「在庫整理」や「商品提供」といった一般的な語句で表現しましょう。応募先とは無関係な専門用語を使っていると、具体的に何の業務なのかがわからず、強みが伝わりにくくなってしまいます。
応募先で役立つ資格や特技
応募先での業務で役立つ資格・特技があれば、それを基にして自己PRを作成することもできます。例えば、家庭教師のアルバイトにおいて、英検など勉強に関する資格を持っていれば、選考では強いアピールとなるでしょう。
特技をアピールする場合は、それがどのような経歴・経験で身に着けたものであるかを必ず記載しましょう。根拠のない特技を挙げても、採用担当者は本当かどうかを見極めることができません。
【場合別】アルバイト用の自己PR例文
学生で初めてのアルバイトの場合
私はアルバイトの経験はありませんが、学業と野球部の活動を両立しており、時間管理には自信があります。また、部活動の厳しい練習で培った根気強さを活かして、常に明るく元気な姿勢でお客様に対応し、迅速に業務を覚えたいと考えています。新しいことに対して積極的に取り組む姿勢を大切にし、職場の一員として貢献できるよう努力します。どうぞよろしくお願いします。(172文字)
初めてのアルバイトでは、職務経験を基にアピールすることはできないため、学校生活の中から自分の強みや人柄が表れたエピソードを軸にして自己PRを作成しましょう。
この例文では、部活動の経験から時間管理と根気強さを強みとして挙げており、それを業務に活かす姿勢まで表現できています。アルバイト未経験の場合は特にやる気が重視されるため、「積極的」や「努力」といったポジティブな言葉選びを心がけましょう。
アルバイト経験のある高校生・大学生の場合
以前は飲食店で接客やキッチン業務を担当し、お客様への迅速かつ丁寧な対応を心掛けていました。また、忙しい時間帯でも冷静に業務をこなし、チームと協力して円滑に進行できるよう努めました。この経験を通じて、問題解決力やコミュニケーション能力、柔軟な対応力を身につけました。貴社のアルバイトでも、これらの経験を活かし、貢献できるよう努力しますので、どうぞよろしくお願いします。(183文字)
アルバイト経験のある学生は、これまでの職務経験をアピールすることが効果的です。未経験と同様に学校生活での経験をアピールしても問題ありませんが、一般的には実務的な内容の方が現場での能力が伝わりやすくなります。
応募先と関連のある職種の経験があれば、それを中心にアピールを組み立てましょう。応募先と関連がない職種の経験しかない場合は、その中での業務を端的に説明し、結果としてどのような学びや強みを培ったのかを説明しましょう。
フリーターの場合
これまでは貴社とは異なる職種での経験を積んできましたが、その中で、お客様への対応やチームワークの重要性を学び、柔軟性を持って業務に取り組むことの大切さを実感しています。また、以前より週5日の稼働を続けていたため、長時間・長期間の勤務にも対応できます。これまでの経験を活かしつつ、新しい挑戦にも前向きに取り組み、さらに成長を目指していきたいと思います。(175文字)
フリーターには一定のアルバイト経験が求められるほか、どの程度の時間の勤務が可能なのかも重要なアピールポイントとなります。
基本的には学生よりも融通が効き、長時間のシフトにも対応できることが期待されるため、その点について記載しておくことが有効です。何らかの事情があり、長時間のシフトが組めない場合には、わざわざ記載する必要はありません。
また、長期で働いてくれる人は歓迎されやすいため、3か月以上の勤務を見込んでいるのであれば、それを明記しておくと良いでしょう。
主婦・主夫の場合
家庭での経験を通じて、効率的な時間管理や柔軟な対応力、細やかな気配りを身につけました。また、家事や育児をしながら培ったマルチタスク能力や計画力も自信があります。これらの強みを活かし、職場でも周囲と円滑に連携し、業務を迅速かつ丁寧にこなしていきたいと考えています。家庭と仕事を両立し、前向きに仕事に取り組んでいきますので、どうぞよろしくお願いいたします。(176文字)
主婦や主夫の方は、家庭の経験がアピール材料になります。これまでにアルバイトや正社員などの経歴がある場合は、その経験をアピールしても良いでしょう。ただし、学生時代のエピソードは基本的に使わない方が無難です。
家庭では様々な力が培われます。自身の家庭での役割を明確にした上で、培った能力を業務にどのように活かすのかを記載することで、有用な人材であることのアピールに繋がります。
【応募業種別】アルバイト用の自己PR例文
飲食
私は大学でのサークル活動を通じて、さまざまな人と接する機会を持ち、コミュニケーション能力を磨いてきました。今回は初めてのアルバイトとなりますが、お客様に笑顔で対応し、楽しんでもらえるよう努力したいと考えています。チームワークを大切にし、周囲と協力しながら業務を進められる自信があります。貴社で接客のスキルを学び、お店の活気を作り出す一助となる所存です。(176文字)
飲食業では作業効率やチームワークだけでなく、お客様に明るく対応するスキルが求められます。
この例文ではアルバイトが未経験でありながらも、大学のサークル活動というコミュニケーションが活発な場で接客業に必要な力を培ったことを伝えられており、応募先に合致するスキルをアピールできています。
カラオケ
以前、カラオケ店でのアルバイト経験があり、接客においてはお客様に楽しんでいただけるよう心掛けていました。お客様との会話を楽しみつつ、空間作りに貢献することが得意です。また、細やかな気配りや臨機応変な対応ができるため、忙しい時間帯でも落ち着いて業務をこなせる自信があります。今後も、より多くの笑顔を提供できるよう努めます。(160文字)
同職種での経験があることを活かし、実際にどのような姿勢で業務にあたっていたかを端的に伝えられている例文です。
アピールするべきポイントを理解して書けているため、採用担当者に強みが伝わりやすく、活躍がイメージできる内容となっています。
具体的な業務内容についてもう少し触れられると、以前にどの程度の業務を任されていたのかがわかり、判断がしやすくなるでしょう。
コンビニ
家庭での経験を活かし、効率的に業務を進めることが得意です。レジ業務や商品の陳列、清掃など、全ての業務において丁寧かつ迅速に対応します。また、家庭内で時間を有効に使うことを心掛けているため、シフト管理やチームでの連携にも柔軟に対応できると考えています。お客様にとって居心地の良い店舗作りに貢献できるよう努力します。(156文字)
コンビニの業務内容に触れつつ、それらを上手くこなす自信を前面に押し出している点が特徴的な例文です。
就業意欲を感じられる文面であり、アルバイト経験は挙げていないものの、熱意が伝わりやすい自己PRになっています。
家庭のどのような経験を基にして、業務に対応できると考えているのかを具体的に示すことで、さらに説得力のある文章に仕上がるでしょう。
接客・販売
私は大学のゼミ活動に参加する中で、チームで目標を達成することを大切にしてきました。接客業の経験はありませんが、販売業務に興味があり、しっかりと学んでいきたいと考えています。物事を覚えるのが早く、積極的に質問して知識を増やしていく姿勢を持っています。お客様に安心していただけるよう、丁寧で親身な接客を心掛けていきますので、よろしくお願いします。(171文字)
志望職種への興味・関心は、直接的な能力のアピールにはなりませんが、意欲のアピールとして高い説得力があります。
特に「学びたい」という意欲は積極性にも繋がり、業務を覚えようと努力することを期待させられるでしょう。
講師・家庭教師
これまで友人や後輩に勉強を教えた経験があり、相手の理解度に合わせた指導が得意です。私自身も学ぶことが好きで、わかりやすく伝える方法を工夫しています。家庭教師として、生徒一人ひとりのペースに合わせて学習指導を行い、成果を実感してもらえるようサポートしていきたいと考えています。誰とでも打ち解けられる性格を活かし、信頼関係を築いていきますので、よろしくお願いいたします。(183文字)
講師や家庭教師では、「わからない相手に教える」という日常では培われにくい能力が求められます。そのため、そうした経験がある方は積極的に記載しましょう。
この例文では、どのような教え方が得意か、どのような工夫をしているかまで明記されており、即戦力として期待の持てる内容となっています。
イベントスタッフ
大学でのボランティア活動を通じて、イベント運営のサポートを行った経験があります。お客様と接する際には、笑顔で対応し、楽しんでもらえるよう努力しています。また、臨機応変な対応力を活かし、イベントの進行をスムーズにサポートできる自信があります。イベントスタッフとして、チームと共に成功に導けるよう全力を尽くします。(155文字)
イベントスタッフのアルバイトは短期や単発の場合が多く、じっくり学ぶ姿勢よりはその場にすぐ適応できるような力が求められやすい傾向にあります。
この例文では大学のボランティア活動の経験に加え、臨機応変な対応力をアピールすることで、すぐに活躍できるような印象を与えられている点が好印象です。
引っ越し
中学から現在までサッカー部に所属しているため体力には自信があり、過去には引っ越しや倉庫作業のアルバイト経験もあります。重い荷物の運搬も問題なくこなし、作業を丁寧かつ迅速に進めることが得意です。また、お客様に対して親切で気配りのある対応を心掛け、ストレスの少ない引っ越しを提供できるよう努めます。今後も安全で効率的な作業を心掛け、仕事に取り組みます。(174文字)
引っ越し業では体力が必要不可欠ですが、運動部に長く所属していることは体力の裏付けとして十分な説得力を持ちます。また、過去に同職種のアルバイト経験もあり、実務も問題なく遂行できることは非常に強いアピールとなるでしょう。
さらに、業務をこなす上でお客様に対する気配りも忘れない姿勢が伝えられており、丁寧な仕事ぶりが想像できる自己PRとなっています。
このように、応募先で特に重視される要素に対するアピールを散りばめることで、その職種への理解度も伝わる効果が期待できます。
コールセンター
以前のアルバイトで接客業を経験し、電話対応のスキルを磨いてきました。細かい作業にも集中できるタイプで、正確で丁寧な対応を心掛けています。コールセンター業務では、電話を通じてお客様の問題を解決し、信頼を得ることを最優先に取り組みます。丁寧で分かりやすい説明を心掛け、お客様にとって安心できる対応を提供していきたいと考えています。(163文字)
別業種で類似した業務に携わった経験をアピールしている例文です。同職種でなくとも、このように関連する業務を基にアピールすることで、経験不足というイメージを与えにくい自己PRを作成できます。
また、業務に携わる上で最優先とすることを明確にしており、志望者の人柄が良く出ている点も好印象を与えやすいポイントです。
電話対応は状況によって内容が大きく変わる業務なので、経験のあるものがどのような電話への対応だったのかを軽く説明できると、より実務的な活躍をイメージしやすくなるでしょう。

アルバイト用の自己PRで気を付けたいポイント
正しい言葉使いを意識する
アルバイト用の履歴書も正式な応募書類であるため、丁寧な書き言葉で書くようにしましょう。応募書類を書き慣れていない学生の場合、話し言葉と書き言葉を混同してしまうことが多いです。
特に、「だから」や「なので」といった接続詞は誤って使いやすい話し言葉であり、見直しても気付けないことがあります。直前の文章を踏まえる場合の接続詞は「そのため」や「したがって」を使うことが適切です。
また、文章の言い切りは「です・ます調」と「だ・である調」のどちらでも問題ありませんが、応募書類全体で統一されている必要があります。自己PRと志望動機で言い切りが異なっていると非常に不自然に見えるため、どちらか片方の言い切りだけを使うようにしましょう。
長すぎる・短すぎるものはNG
自己PRには基本的に文字数の指定がありませんが、記入欄いっぱいに小さな文字を敷き詰めたり、半分以上が余白となっていたりすると悪い印象を与えやすいです。
自己PRは就業の意欲を示す項目でもあるため、読みにくいものやアピールが適当に見えるものは相応しくありません。
およそ200字程度を目安として、長すぎず短すぎない文量で自己PRをまとめ、端的に自分の強みと意欲を伝えられるように意識しましょう。
関係のない自慢話はしない
自己PRで自分を有用に見せようとして、エピソードをいくつも盛り込むのは逆効果になります。全てのエピソードから共通して1つの学びを得たというのは考えにくく、単なる自慢話として受け止められる可能性が高いためです。
また、エピソードを紹介するだけで、そこから得られた学びへ繋げずに終わってしまうのも同様に不適切です。
自己PRや志望動機においては、エピソードと学び・成果はセットで記述するべきものです。自慢話だけで自己PRが終わらないように注意しましょう。
志望動機や面接のやり取りと矛盾しないようにする
応募書類の中の記述に矛盾があると、信頼を大きく損ねます。特に自己PRと志望動機は重視される項目なため、この2つの内容に矛盾が出ないようにする必要があります。
また、応募書類に記入した内容は、面接で深掘りされる可能性があります。その際、記入内容と合致しない返答をしてしまうと、不信感を抱かれ、採用を見送られてしまうこともあるでしょう。
自己PRに虚偽の内容を書かないのはもちろんのこと、志望動機などの項目との矛盾もないように良く見直し、面接でどの部分について聞かれてもスムーズに受け答えができるよう備えておきましょう。
アルバイト用でも自己PRは効果的に仕上げよう
アルバイトだからといって適当に作成した応募書類を提出することは、採用の確率を落とすだけでなく、応募先に対しても大変失礼な行為です。
どのような職種であっても、仕事に貢献できる人材であることを自己PRで表現することは必須です。正確に自分の魅力を伝え、業務に対して真剣に取り組める姿勢をアピールする必要があります。
この記事で紹介した基本の書き方や例文を参考に、自分の強みと個性がしっかりと伝わる自己PRを作成して選考に臨みましょう。
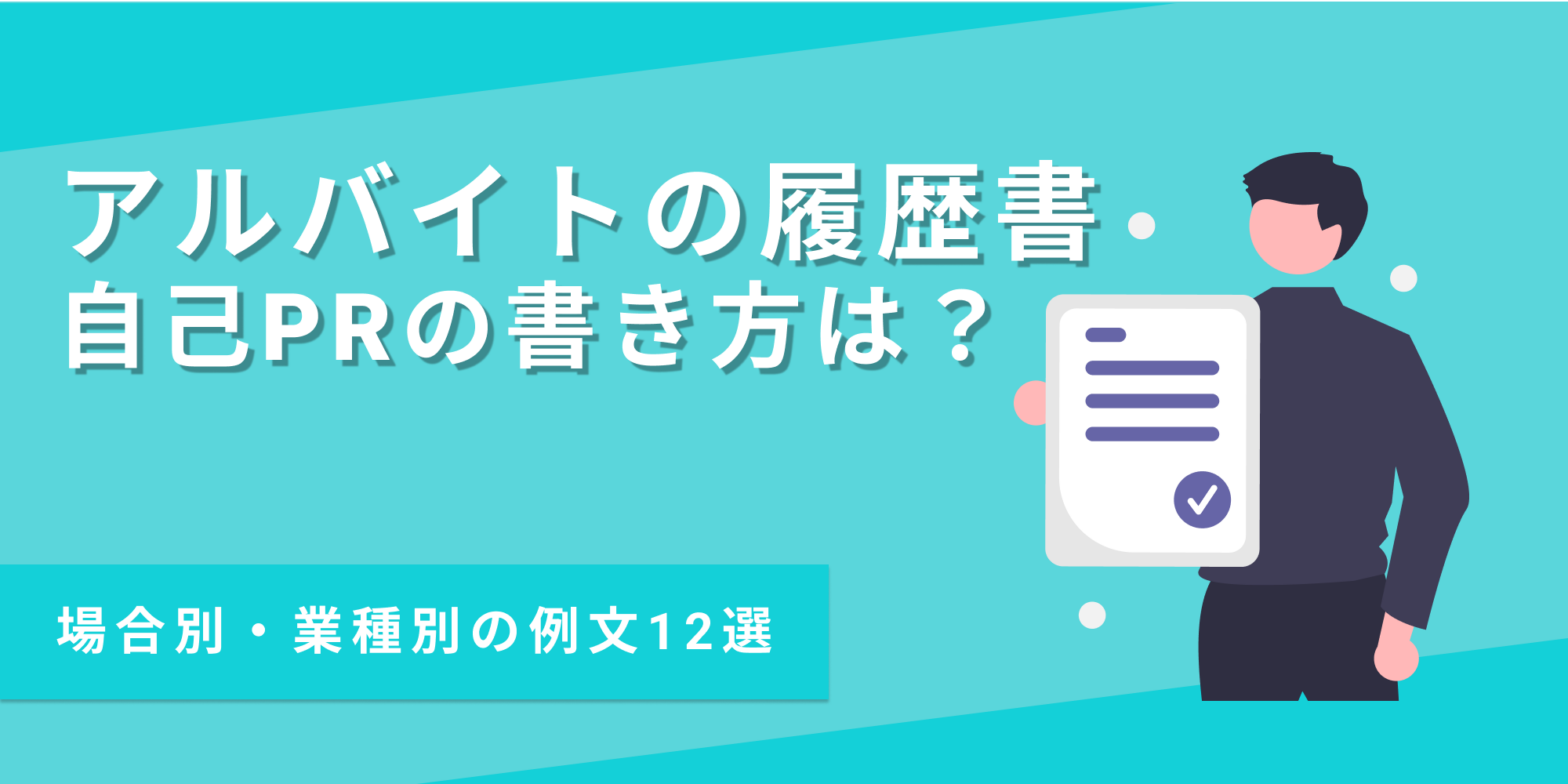









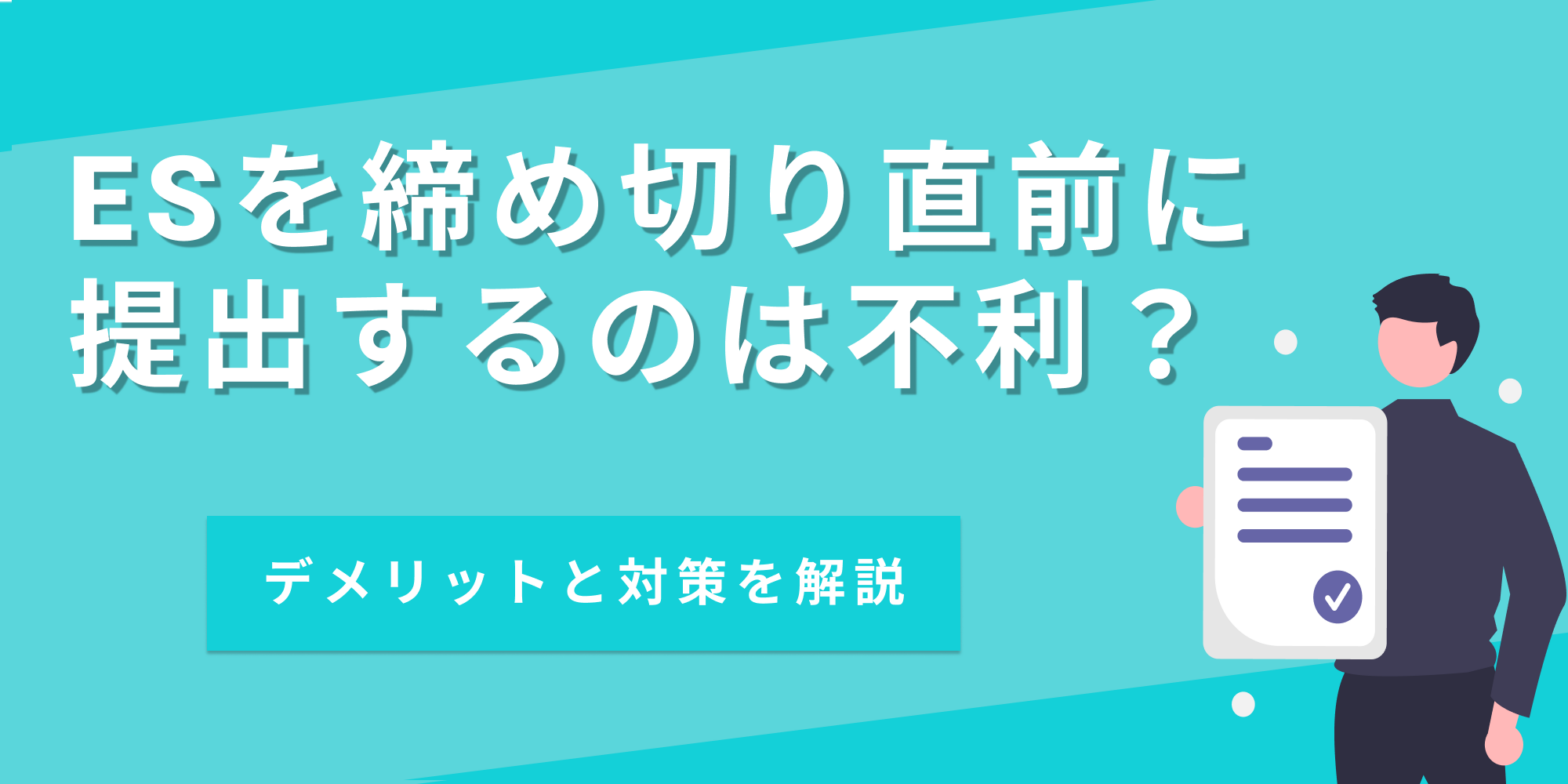

-1568x784.png)