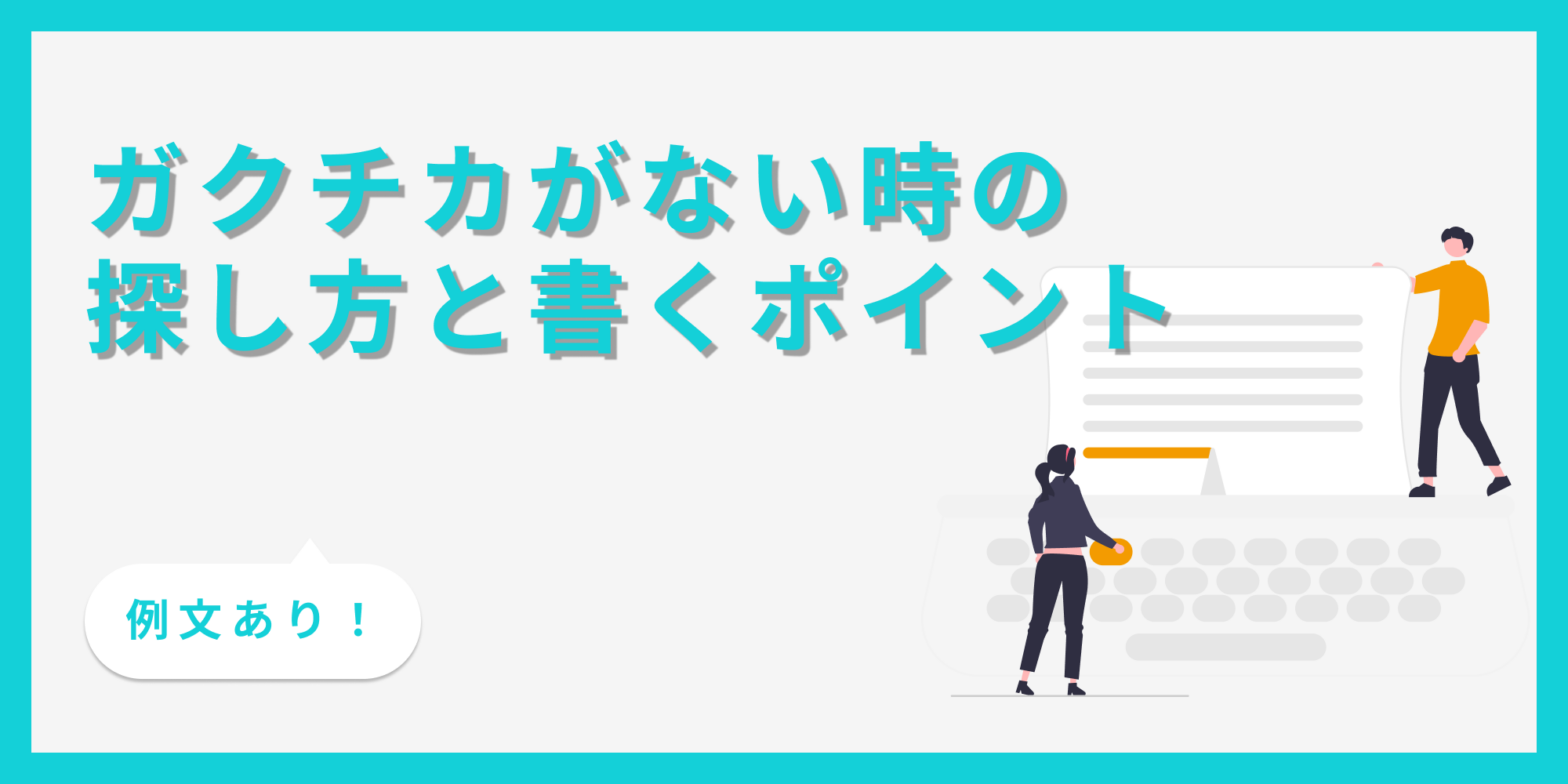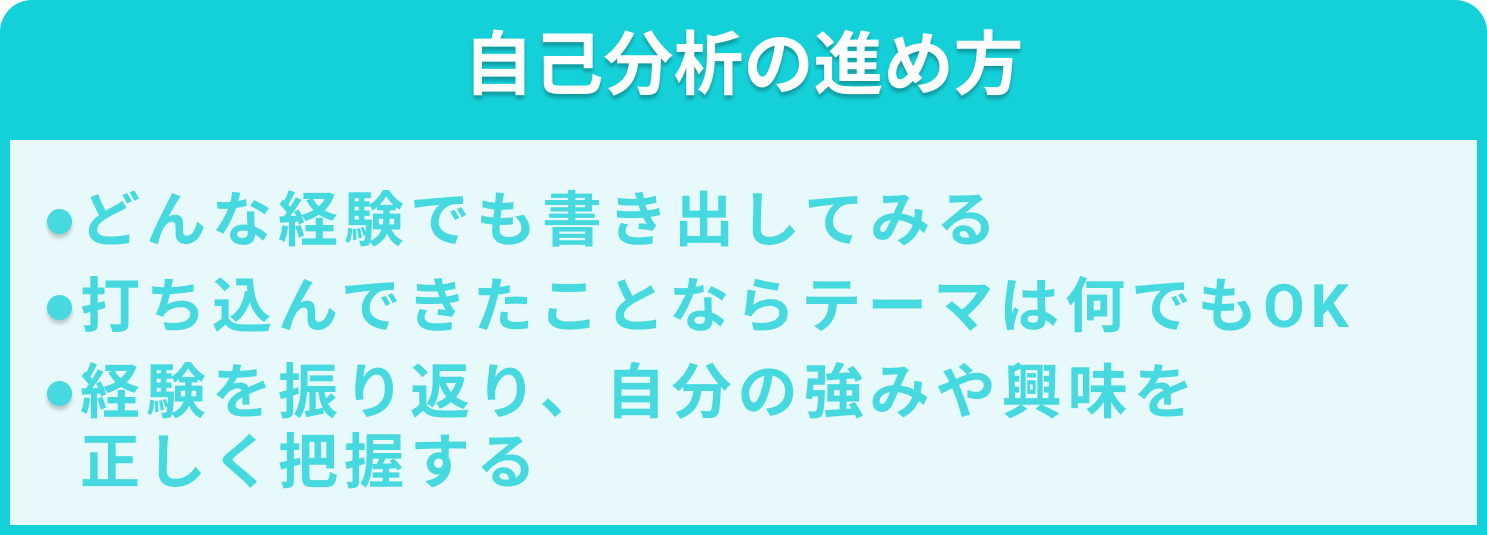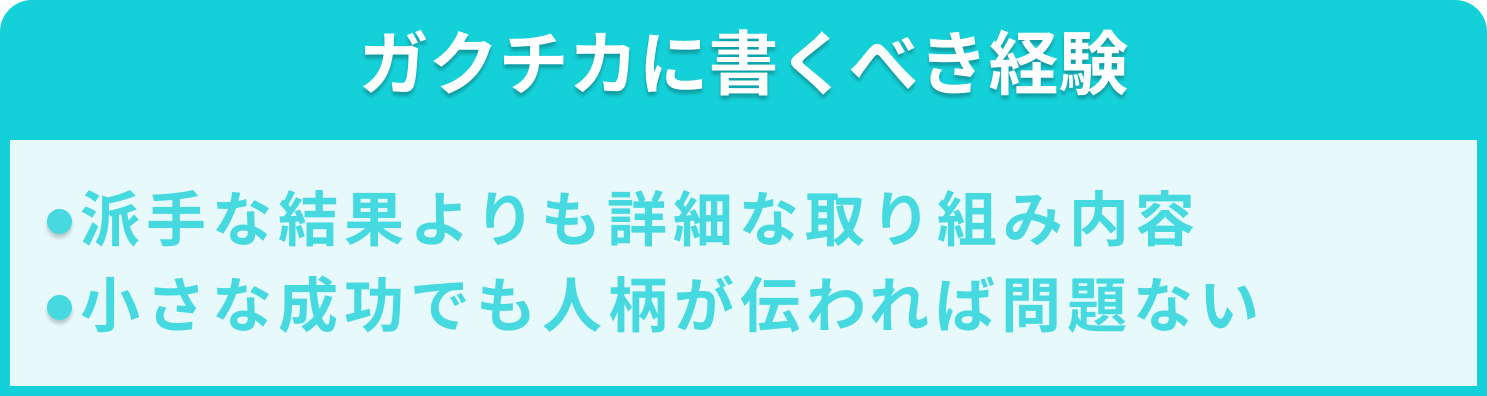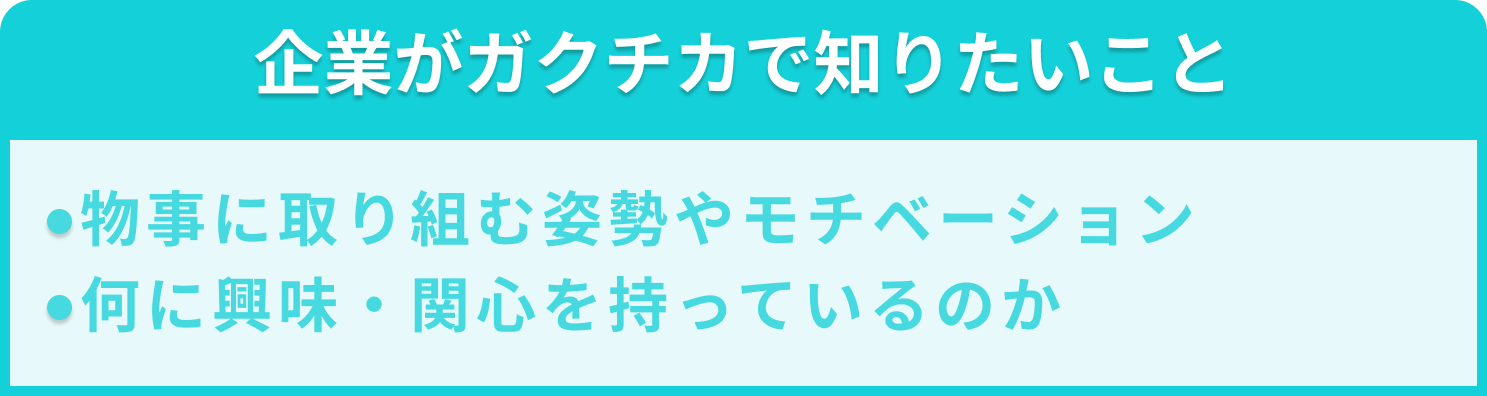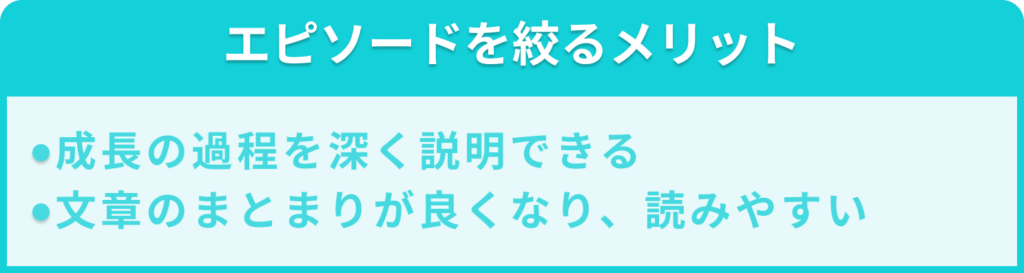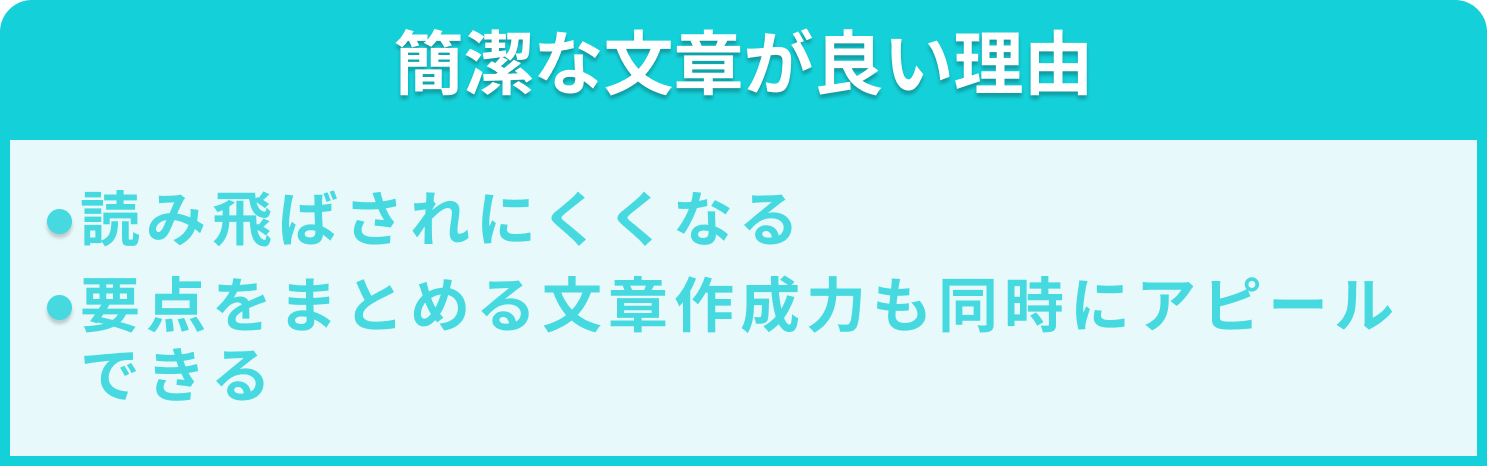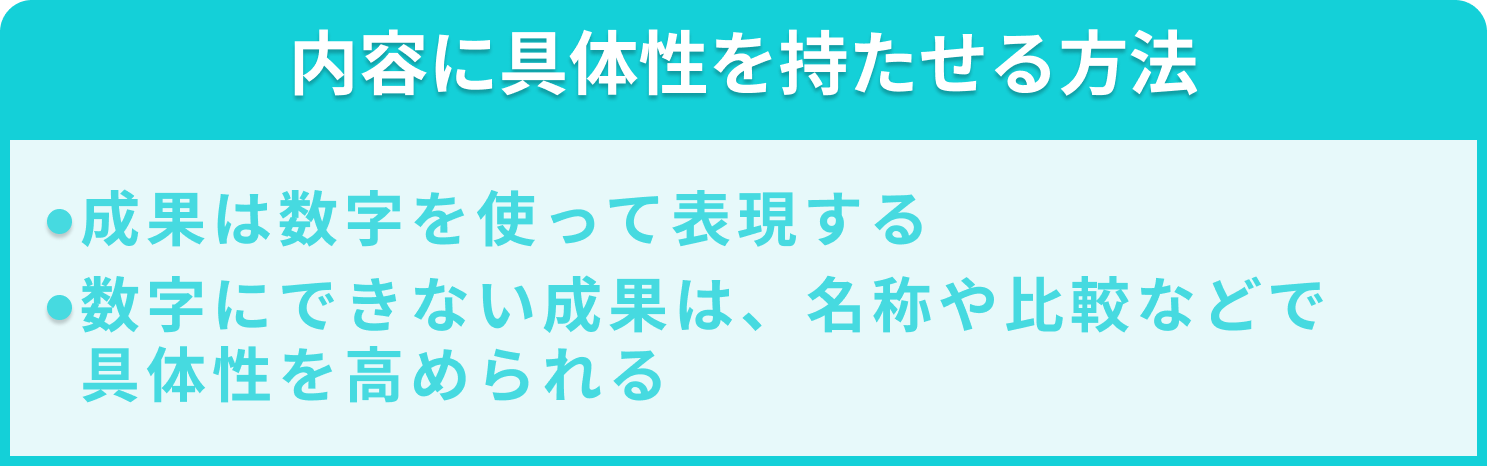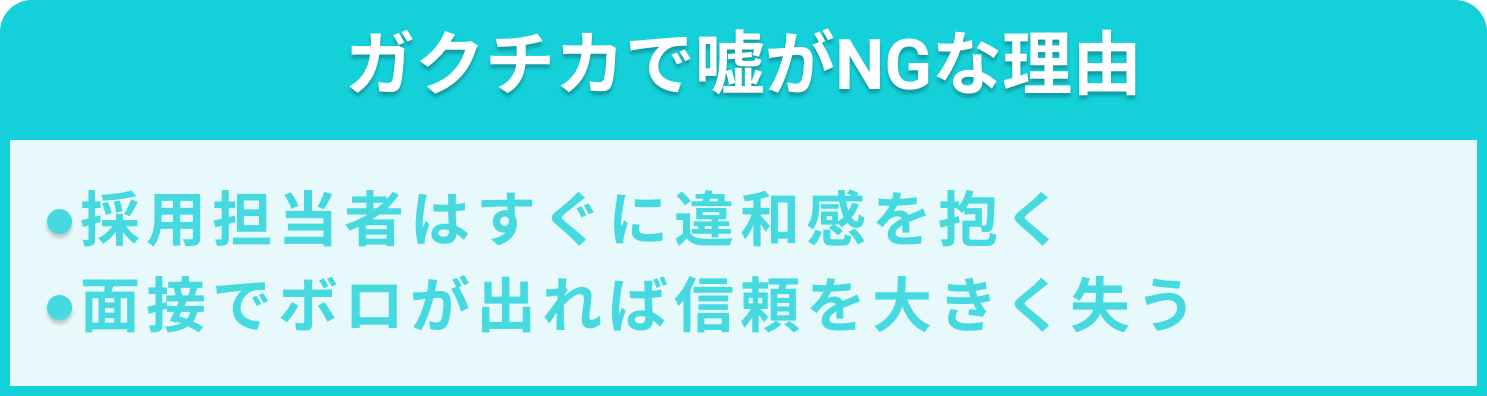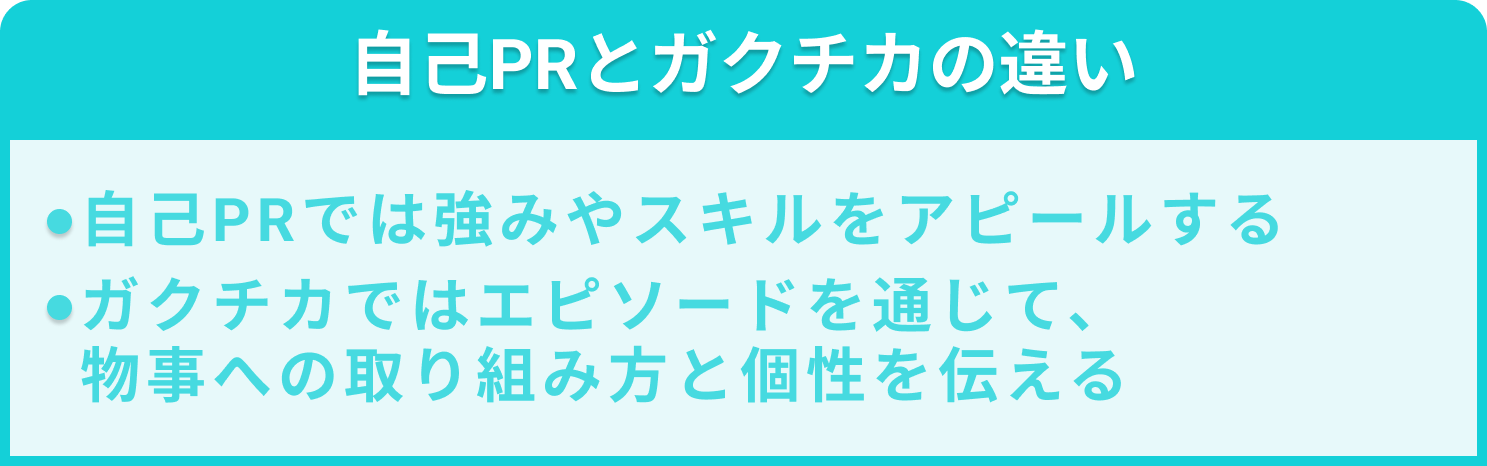ESでの志望動機は、あなたの熱意や適性を伝える絶好のチャンスです。しかし、多くの学生が「どのように書けば良いのだろう」と悩んでいます。
志望動機は単に「興味がある」という内容だけではなく、なぜその企業で働きたいのか、どのように貢献できるのかを具体的に示す必要があります。また、企業の求める人物像に対して、自分の経験を結びつけるための言葉選びがカギとなります。
本記事では志望動機の書き方のポイントを、実際に使える例文とあわせて解説します。志望動機がしっかり伝われば、選考の突破率もグッとアップします。自分の思いが伝わる志望動機を作成しましょう。
ESで志望動機が重要な理由とは?
企業へ熱意を伝えられる
志望動機は、企業への熱意を直接的に伝える絶好の機会です。企業は、応募者が自社にどれだけ真剣に取り組む意欲を持っているのかを重要視しています。
自分の言葉で、なぜその企業を選んだのか、どのような思いを持っているのかを具体的に示すことで、熱意が伝わりやすくなります。例えば、企業の理念やビジョンに共感した理由や、特定のプロジェクトに魅力を感じたエピソードなどを盛り込むことで、あなたの真剣さがより強く伝わります。
自分の適性をアピールするためのチャンス
志望動機は、自分がその企業にどれだけマッチしているかをアピールする機会でもあります。過去の経験やスキルを具体的に示すことで、企業が求める人物像と自分自身を結びつけることができます。
例えば、自分が大学で学んできたことやインターンシップでの経験を元に、「このスキルを活かして、貴社のプロジェクトに貢献できる」といった具体的な例を挙げることで、説得力が増します。このように、自分の適性をしっかりアピールすることが、選考を有利に進めるカギとなります。
選考の次のステップのカギとなる
志望動機は選考の次のステップに繋がる重要な要素です。明確で具体的な志望動機があれば、面接官に良い印象を与え、次の選考へ進む可能性が高まります。逆に、志望動機が不明確であったり、企業への理解が浅いと、選考に不利になることがあります。
はっきりとした志望動機があれば、自分に自信を持って面接に臨むことができ、さらにその自信が面接官にも伝わります。志望動機があなたの就職活動の流れを左右することを意識して、しっかりと準備しましょう。
他の応募者との差別化を図るため
多くの応募者がいる中で、自分を目立たせるためには志望動機を他の人と差別化することが重要です。同じような経歴やスキルを持つ学生が多い中で、独自の経験や視点を表現することで、明確な差別化を図ることができます。
例えば、特定の経験がどのように自分の考え方に影響を与えたのかを具体的に語ることで、他の応募者とは一線を画すことができるでしょう。あなた自身をしっかりとアピールし、内定獲得に向けての強力な武器にしましょう。
志望動機を書く前に考えるべき3つのポイント
自己分析を徹底する
志望動機を書く際には、まず自分自身をよく理解することが重要です。自己分析を通じて、自分の強みや弱み、価値観や興味を明確にしましょう。
これまでのどのような経験が自分を成長させたのか、どのようなスキルを身に付けてきたのかを振り返ることで、自分が何を求めているのかが見えてきます。そして、具体的なエピソードや成功体験を思い出すことで、志望動機に具体性を持たせることができます。
自己分析を徹底することで、自分の言葉で伝えられる志望動機を作る基盤が整います。
企業研究をしっかり行う
志望動機を書くためには、志望する企業についてしっかりと研究することが不可欠です。企業の理念、ビジョン、事業内容、最近のニュースなどを把握し、どのような企業であるかを理解しましょう。
また、業界のトレンドや競合他社との違いを知ることも大切です。その企業が特に優れている点や独自の強みを把握することで、企業への関心をアピールできます。企業に対する理解が深まれば、面接でも自信を持って話すことができるでしょう。
自分と企業のマッチングポイントを明確にする
自己分析と企業研究を行った後は、自分と企業のマッチングポイントを明確にしましょう。自分の経験やスキルがどのように企業の求める人物像と合致するのかを照らし合わせ、その具体的なポイントを志望動機に組み込んでいきます。
例えば、企業の取り組みが自分の興味や経験にどのように結びついているのかを示すことで、企業側に「この人はうちにピッタリだ」と思わせることができます。マッチングポイントを明確にすることで、志望動機に一貫性が生まれ、より魅力的な内容になります。
志望動機の書き方の基本構成
①志望先の企業を選んだ理由
まず最初に、なぜその企業を選んだのかを明確に述べることが大切です。この部分では、企業の理念やビジョン、事業内容に対する共感や興味を具体的に示しましょう。
例えば、企業のプロジェクトやサービスが自分にどのように響いたか、自分の価値観や将来の目標とどう結びついているのかを語ると良いです。また、企業の成長性や業界での位置付けなど、自分がその企業に魅力を感じる理由を明確にすることで、企業への熱意が伝わります。
②志望理由を裏付ける具体的なエピソード
次に、志望理由を裏付けるための具体的なエピソードを紹介します。ここでのエピソードは、自分の経験やスキルを具体的に示すものであるべきです。オリジナル性を高める志望動機に仕上げるためには、このエピソードが重要です。
例えば、過去のアルバイトやインターンシップでの経験、自分が関わったプロジェクトの成果などを挙げて、その中で学んだことや成長した点を述べると良いでしょう。エピソードを通じて、あなたの人柄や価値観が伝わると同時に、企業が求める人物像とどのように合致しているかを示すことができます。
③入社後のビジョンや目標
最後に、入社後のビジョンや目標について触れます。自分がその企業でどのように成長したいのか、どのような貢献をしたいのかを具体的に述べることで、企業に対する真剣さや長期的な視点を示すことができます。
明確な目標を持っていることを伝えることで、企業側はあなたが将来の仲間としてどれほど価値をもたらしてくれるかをイメージしやすくなります。最後の一文によって、志望動機全体がより好印象を与える内容に仕上がります。
採用担当者に響く志望動機の書き方のコツ
冒頭で結論(志望理由)を示す
志望動機は最初に結論を述べることで、採用担当者に強い印象を与えることができます。例えば、「貴社の〇〇という理念に共感し、志望しました」といった具体的な言葉で始めると良いでしょう。
最初に自分の熱意や目的を明確にすることで、読み手の関心を惹きつけることができます。また、その後の内容も論理的な流れを作りやすくなります。結論を先に示すことで、読み手はあなたの意図を理解しやすく、興味を持って読み進めてくれるでしょう。
企業のどこに魅力を感じたのかを伝える
企業への志望動機を考える際、その企業にどのような魅力を感じたのかを具体的に伝えることが重要です。志望動機に何を書けば良いのかわからないと悩んでいる場合は、自分が思う志望企業の魅力を書き出してみましょう。
自分の思いを具体化し、感銘を受けた理由を述べることで、企業に対する理解と情熱をアピールできます。これにより、あなたが企業との相性をしっかり考えたうえで応募していることが伝わり、印象を強く残すことができるでしょう。
前向きな表現を心がける
志望動機を書くときは、前向きな表現を心がけましょう。ポジティブな言葉遣いは、あなたの情熱や意欲をアピールするのに役立ちます。「挑戦したい」「貢献したい」「成長したい」といった前向きなフレーズを使うことで、読み手に自分のやる気を伝えることができます。
謙虚な姿勢は大切ですが、自分を卑下する必要はありません。ネガティブな表現を避け、可能性や希望を強調し、あなたの自信を感じさせることが大事です。未来に向けた意気込みを示すことで、採用担当者に良い印象を残すことができます。
企業に貢献できることをアピールする
志望動機では、自分が企業にどのように貢献できるかを具体的に述べます。自分のスキルや経験を活かし、どのような形で企業に価値を提供できるかを考え、明確に表現しましょう。
例えば、「私の〇〇という経験を活かして、貴社の〇〇プロジェクトに貢献したいと考えています」というように、自分の強みを企業のニーズに結びつけてアピールすることが大切です。具体的に自分の役割をイメージさせることで、採用担当者に対して「この人は本当に役立ちそうだ」と思わせることができます。
志望動機を書くときの注意点
抽象的な表現を使わない
志望動機を書く際は、抽象的な表現は避けなければなりません。「頑張ります」「興味があります」といった一般的なフレーズではなく、具体的な経験や意図を示しましょう。
このような抽象的な表現は、なぜその企業でなければならないのかが不明確であり、内容が薄いと捉えられる恐れがあります。また、企業が求める基準に合致しているかどうかを明確に示すことができず、選考基準を満たさないと判断されてしまうかもしれません。
具体性を持たせることで、採用担当者に対してあなたの志望動機がより信頼性のあるものとして伝わります。成果やスキルなどを示す際には、数字を用いて説明するとより効果的です。
例文はそのままコピペしない
志望動機の書き方がわからないからといって、インターネット上にある例文をそのままコピペするのは絶対にNGです。例文はあくまで参考にするものであり、自分の言葉や経験を反映させることが大切です。
コピペしてしまうと、あなた自身の意図や思いが伝わらず、内容が一般的で薄っぺらい印象を与えてしまいます。また、コピペの内容では個性が消えてしまい、他の応募者と差別化することができません。
多くの応募者から選ばれるためには、独自性のある志望動機を書く必要があります。自分自身のストーリーを自分の言葉で語ることで、あなたの魅力を最大限に引き出すことができます。
指定文字数を守る
志望動機を書く際には、指定された文字数の制限を守ることも重要です。企業によっては文字数が決められている場合があります。そのため、企業の指示にしっかりと対応することが大切です。
指定された文字数を守れないことは、指示やルールに従う能力がないと捉えられてしまいます。また、今後の業務においても適応力やコミュニケーション能力がないのではないかというマイナスな印象を与えかねません。
制限文字数を守ることは、企業へのリスペクトを示すことでもあります。志望動機を書き始める前に字数を確認し、その範囲内でしっかりと要点を絞り、効果的に自分をアピールする文章を心がけましょう。
誤字・脱字に注意する
誤字や脱字には細心の注意を払って志望動機を書きましょう。志望動機はあなたの自己アピールの場であり、きちんとした文章であることが求められます。そのため、誤字脱字のある文章は、印象を大きく損ねる要因となります。
書き終えたら必ず見直しを行うようにし、可能なら他の人にチェックをしてもらうことも効果的です。仕事に対して真剣で丁寧な姿勢をアピールするためにも、ミスがないかしっかりと確認しましょう。
【業界別】ESの志望動機の例文
例文①IT
私が貴社を志望する理由は、IT企業としてグローバル展開し、最先端技術と社会貢献を両立している点に魅力を感じたためです。特に、貴社の開発した途上国向けの教育支援アプリの開発に感銘を受けました。大学での国際開発研究と、学生時代のNPOでのIT教育ボランティア経験から、技術を通じた社会貢献に強い関心を持っています。入社後は、海外駐在の機会を通じて現地ニーズに即したITソリューション開発に携わり、プログラミングスキルと語学力を活かして貴社の国際プロジェクトに貢献したいと考えています。(250字以内)
この例文のように、企業の具体的なプロジェクトや特徴を挙げることで、企業に対する関心を示すことができます。また、自分の経験を明確に関連付け、「この経験を活かしたい」と具体的に述べることで説得力が増します。最後に、貢献意欲も伝えて、熱意を込めた志望動機を作成しましょう。
例文②食品
貴社の健康食品開発と海外展開への注力に魅力を感じ、志望いたしました。大学で栄養学を専攻し、食の安全性と栄養価の重要性を学ぶ中で、貴社の「ナチュラルプラス」シリーズに注目しました。この製品群が体現する「自然の力を活かした健康づくり」という理念に深く共感しています。私は大学時代、食品メーカーでのインターンシップを通じて商品企画や市場調査のスキルを磨きました。この経験を活かし、「食で世界をつなぐ」というビジョンの下、貴社の営業部門で健康食品の価値を国内外に伝えたいと考えています。(250字以内)
この例文では、企業の特長と自分の専門性を効果的に結びつけています。最初に「健康食品開発と海外展開への注力」と具体例を挙げることで、企業のどの部分に魅力を感じているのかがはっきりと伝わります。
また、大学での専攻やインターンシップ経験を具体的に示すことで、自分のスキルをアピールできます。企業に通じる経験やスキルを盛り込むことで、より効果的な内容に仕上がります。
例文③商社
貴社の高品質な化学製品と世界規模での事業展開に強く惹かれました。特に、環境配慮型製品の開発や持続可能な生産プロセスへの取り組みに共感しています。大学での有機合成実験を通じて品質管理の重要性を実感し、その経験が貴社の品質へのこだわりへの共感へと繋がりました。入社後は、居酒屋のアルバイトで培ったコミュニケーション力を活かし営業として顧客ニーズを的確に把握し、最適な製品提案を行うことで企業価値向上に貢献したいと考えています。将来的には海外駐在の機会を得て、グローバルな視点でビジネスを展開する力を養い、世界中の人々の暮らしを豊かにしていきたいです。(300字以内)
商社企業の場合は、多岐にわたる事業を展開しているため、企業の事業領域や商品に対する興味を踏まえ、どのような分野で貢献したいかを明確にすることが大切です。
また、国際的なビジネスが中心ですので、グローバルな視点を持つ意欲を強調し、企業にとっての長期的な価値を示すことも効果的です。
例文④銀行
私が貴行を志望する理由は、地域に根差した金融機関としての役割にあります。大学で地域経済を学び、貴行のSDGs推進や地域創生への取り組みに深く共感しました。特に、フィンテックを活用した地元企業支援や、顧客との対面コミュニケーションを重視する営業スタイルは、私の「技術と人間性を融合させた金融サービスを提供したい」という思いと合致しています。入社後は法人渉外部門で、地元企業の経営課題解決に尽力したいと考えています。大学での地域経済分析の経験を活かし、企業の潜在的ニーズを掘り起こし、最適な金融ソリューションを提案することで、地域経済の活性化に貢献したいと考えています。(300字以内)
この例文では、地域に根差した銀行の役割への理解と共感を強調しています。特に、大学で学んだ地域経済と、銀行のSDGs推進や地元企業支援への取り組みを結びつけることで、具体的な関心が伝わります。また、個人的なビジョンを示し、自分の価値観が銀行の理念と一致していると印象付けることも効果的です。
例文⑤出版
貴社のファッション誌の国際的な影響力とデジタル戦略に強く惹かれ、志望いたしました。大学でファッション文化を学び、雑誌編集のインターンを通じて、日本のファッションの独自性と世界発信の重要性を実感しました。特に貴社の海外向けSNS戦略に注目しており、語学力を活かして、日本のファッションを世界に伝える架け橋になりたいと考えています。デジタルとプリントの両メディアを駆使し、グローバルな視点を持つ編集者として、貴社の国際展開に貢献したいと考えています。(250字以内)
出版業界の志望動機を書く際には、業界への理解を示すことが重要です。具体的なトレンドや課題に触れ、自分が興味を持つジャンルや媒体を明確にすることで、関心をアピールできます。また、インターンシップやアルバイトなどの経験を挙げ、その実務能力がどのように役立つかを具体的に述べましょう。
例文⑥保険
私が貴社を志望する最大の理由は、家族の病気を通じて保険の重要性を実感したことです。貴社の幅広い商品ラインナップと、特に医療保険における革新的な取り組みに強く惹かれました。他社にない充実したサポート体制も、私の志望を後押ししています。入社後は、自身の経験を活かし、お客様一人ひとりのニーズに合わせた最適な提案を心がけます。特に医療保険の重要性を伝え、お客様の安心な人生設計に貢献したいと考えています。将来的には、貴社で最も信頼されるRMとなり、保険を通じた社会貢献という理念の実現に全力を尽くしたいです。(250字以内)
最初の志望理由で自分の経験を伝えることで、読み手側の興味を一気に惹きつける書き出しになっています。お客様に寄り添う業界だからこそ、お客様目線での経験を持っていることは大きな強みとなるでしょう。入社後、具体的にどのような存在になりたいかを伝え、企業に対する熱意をアピールすることが大切です。
例文⑦コンサル
貴社の幅広い業界に対応するワンストップソリューションに強く惹かれ、志望いたしました。大学でのプロジェクト研究を通じ、複雑な経営課題解決の面白さを実感し、コンサルティングの道を志しました。特に貴社のデジタル戦略支援の実績に感銘を受け、自身のITスキルを活かせると確信しています。「日本の産業競争力向上」という思いは貴社の理念と合致し、入社後は大型案件に携わり、主体的に考え抜く姿勢で自己成長と共に貢献したいと考えます。グローバルな視点と幅広い知識を獲得し、将来は日本を代表するコンサルタントを目指します。この志を胸に、貴社の一員として全力で邁進する所存です。(300字以内)
自分が思い描く将来と合致している部分や、企業に強く惹かれた部分を伝えることで、「この企業ではないといけない」という印象を強く残せます。コンサル業界は多様な企業があるため、「他の企業でも良いのでは」と思われるような志望動機を書かないように注意しましょう。
例文⑧証券
貴社の国内外における強固な事業基盤と、フィンテックを活用した革新的な金融サービスに深く感銘を受け、志望しました。地元の金融セミナーで貴社社員の方から伺った実力主義の社風と地域貢献への熱意に強く共感しました。大学時代のボランティア活動を通じて地域活性化の重要性を実感しており、証券アナリスト資格の取得を目指す中で培った金融知識を活かし、地元経済の発展に貢献したいと考えています。入社後は、ESG投資の推進や海外展開に携わり、持続可能な社会の実現と地域経済のグローバル化に尽力します。貴社の先進的なDX戦略と私の熱意を融合させ、新たな金融サービスの創造に挑戦したいです。(300字以内)
企業が取り組んでいることやプロジェクトなどに触れることで、企業に対する理解力をアピールできます。また、企業や業界内で役立つ資格の保有を伝えることで、自分の専門性の高さをアピールすることにも繋がります。このように企業研究を徹底することで、より効果的で内容の濃い志望動機が作成できます。
例文⑨製薬
私が御社を志望する理由は、国内外で高いシェアを誇る製薬企業としての実績と、革新的な研究開発力にあります。幼少期に重い病気を経験し、医薬品の力で回復できた経験から、病気で苦しむ人々を減らしたいという想いを持ち続けてきました。特に、御社の抗がん剤開発への取り組みに深く共感しています。入社後は、MRとして患者さんに寄り添い、適切な医薬品情報を提供したいと考えています。大学での生命科学の学びを活かし、誰にも負けない医薬品のスペシャリストとなることで、貴社の更なる発展と人々の健康に貢献していきたいです。(250字以内)
幼少期の自分の経験と、企業の取り組みを結びつけることでより強い印象を与える志望動機となります。そして最後に、これまでの経験や学びをどう活かしていくのかを具体的に伝えることで、採用担当者にあなたの入社後の活躍をイメージしてもらいやすくなるでしょう。
例文⑩不動産
貴社の「顧客ニーズに応える街づくり」という理念に深く共感し、志望いたしました。地元の再開発事業で貴社の取り組みを知り、地域特性を活かしつつ住民ニーズに応える姿勢に感銘を受けました。私自身、大学でまちづくり学を専攻し、地域活性化プロジェクトに参加した経験があります。
入社後は、デベロッパーとして地域の方々と密接に関わり、彼らの声を丁寧に拾い上げながら、持続可能で魅力的な街づくりに貢献したいと考えています。貴社の先進的なスマートシティプロジェクトにも強く興味を持っており、テクノロジーを活用した未来志向の街づくりにも挑戦したいと考えています。将来的には、不動産のプロフェッショナルとして成長し、地域社会と企業をつなぐ架け橋となることを目指します。(350字以内)
不動産業界や企業に通ずる大学での専攻や、プロジェクトの経験がある場合は積極的に伝えましょう。専門性の高い経験や学びがあることは、不動産業界のような専門的な業界を志望するにあたって大きな強みです。
加えて、どのような業務やプロジェクトに対して興味を持っているのかを伝えることで、長期的な視点を持っているかをアピールできます。
例文⑪自動車
貴社の革新的な技術開発と世界市場への挑戦姿勢に強く惹かれ、志望しました。大学での自動車工学の学びと、学生フォーミュラでのEVマシン開発経験を通じ、日本の技術力の高さを実感しました。この経験を通じ、日本の高度な技術力で世界に貢献したいという思いが強くなりました。貴社はその技術力でグローバル市場に挑戦し続けており、私も国際的視野を持つエンジニアとして貢献したいと考えています。入社後は、新興国市場開拓に携わり、環境に配慮したモビリティソリューションの普及に尽力したいと思います。また、自身のAI・IoT分野での知識を活かし、次世代モビリティ開発にも携わりたいです。グローバルな視点と専門性を磨き、日本のものづくりの未来を担う一員として成長していきます。(350字以内)
大学での経験と志望動機を結び付けることで、より説得力のある内容になります。国際化している自動車業界だからこそ、グローバルな視点を持つことは非常に大きなポイントとなります。入社後、どのような業務に携わりたいのかを伝えて、貢献意欲が高いことをアピールしましょう。

例文⑫広告
私が貴社を志望する理由は、クリエイティビティとプロデュース力の卓越性にあります。大学のマーケティング講座で貴社の革新的な広告キャンペーン、特に最近のSDGs推進プロジェクトを学び、その創造性と社会貢献性に深く感銘を受けました。学生時代のインターンシップで得た経験を活かし、自身のアイデアで勝負できる貴社こそ、私の理想の舞台だと確信しています。
入社後は、急成長するデジタル広告領域で独創的な企画を提案し、データ分析力を駆使してクライアントの課題解決に貢献したいと考えています。将来的には、ナショナルクライアントを担当し、大規模プロジェクトで創造性を最大限に発揮したいです。貴社の先進性と私の創造力を武器に、ユーザーの記憶に残る広告を展開していきます。(350字以内)
大学時代の経験や学びに触れながら、志望企業が自分の理想的な職場であるということをアピールすることは非常に効果的です。企業研究を徹底的に行うことで、その企業が取り組んでいる具体的な業務内容を理解でき、志望動機に繋げることができます。
志望企業で取り組みたい業務やプロジェクトがある場合は、最後の部分に記載することでより印象強い内容になるでしょう。
例文⑬新聞
貴社を志望する理由は、世界最大の発行部数を誇りながら公平中立な報道姿勢を貫く姿勢にあります。大学での新聞部活動を通じて、事実を正確に伝える重要性を学び、貴社の「事実を書いた上で読者に委ねる」方針に深く共感しました。特に、最近の社会問題に関する多角的な報道に感銘を受けています。
入社後は記者として、多様な分野での取材活動に携わり、私の語学力と異文化理解を活かしてグローバルな視点から信頼される記事を執筆したいと考えています。また、デジタル化が進む中で、若年層向けのデジタルコンテンツ開発にも貢献したいと思います。
貴社での経験を通じて、公正かつ深い洞察力を持つジャーナリストとして成長し、報道の力で社会に貢献することを目指します。(350字以内)
志望理由として、その企業がどのような特徴・方針を掲げているのかに触れることは非常に有効です。この場合は、世界最大の発行部数を誇る企業であることから、自分の語学力や異文化理解をアピールできています。志望企業が求める人物像に当てはめて志望動機を書くことを意識しましょう。
例文⑭人材
私が貴社を志望する理由は、多様な労働雇用の課題に総合的に取り組む事業姿勢にあります。特に、AI技術を活用した革新的なマッチングシステムに強く惹かれました。就職活動を通じて人生の転機に直面し、その過程で貴社の存在を知り、人々のキャリア実現を支援する姿勢に共感しました。大学時代のインターンシップで培ったコミュニケーション能力を活かし、入社後はクライアントと求職者双方のニーズを的確に把握し、最適なマッチングを実現したいと考えています。また、データ分析スキルを磨き、AIシステムの改善にも貢献したいです。貴社で経験を積むことで、テクノロジーと人間力を併せ持つ人材のプロフェッショナルとして成長し、社会課題の解決に尽力します。(350字以内)
大学時代のインターンシップ経験から得たスキルと、入社後に実現したいことを結びつけて志望企業に対する熱意の高さをアピールしています。また、入社後も継続してスキルを磨いていきたいことを伝えることで、貢献意欲が高いことをアピールでき、非常に印象の良い志望動機となっています。
例文⑮通信
国内随一の光通信基盤と固定ネットワークシェアNo.1の強みを活かし、自身の「技術で地域に貢献したい」という思いを実現したいと考え、貴社を志望しました。大学でITと社会課題の関連性を学び、特に災害時の情報システム構築に関する研究を行う中で、御社の幅広いソリューションが様々な問題解決に貢献していることに感銘を受けました。安心を支える通信インフラの重要性を強く認識し、この分野で貢献したいと考えています。入社後は、安定した通信環境の提供を通じて、災害時の情報伝達や5G・IoT技術を活用した遠隔医療など、人々の安全に直結するサービス開発に携わりたいです。貴社の先進技術と私の研究経験を活かし、社会に貢献できる人材へと成長していきます。(350字以内)
大学時代に学んできたことが志望企業に通ずる内容であればあるほど、選考時には有利となります。この企業に入るために努力してきたということが伝わる志望動機を作成することで、他の応募者との差別化を図ることができます。企業にとってメリットとなる自分の経験を振り返ってみましょう。

志望動機は自分の言葉で熱意を伝えることが大切!
志望動機は、あなたの熱意や個性を企業に伝える重要な部分です。他の候補者と差別化を図るためには、自分の言葉で表現することが不可欠です。具体的な経験やスキルを盛り込むことで、なぜその企業に魅力を感じ、どのように貢献できるかを明確に示すことができます。
抽象的な言葉や他者の言葉を使わず、自分自身の価値観や目標を反映させることで、採用担当者に真剣な思いが伝わります。企業への理解を深めながら、あなたの意欲を伝え、選考の成功に繋げましょう。
-1568x784.png)









-1568x784.png)





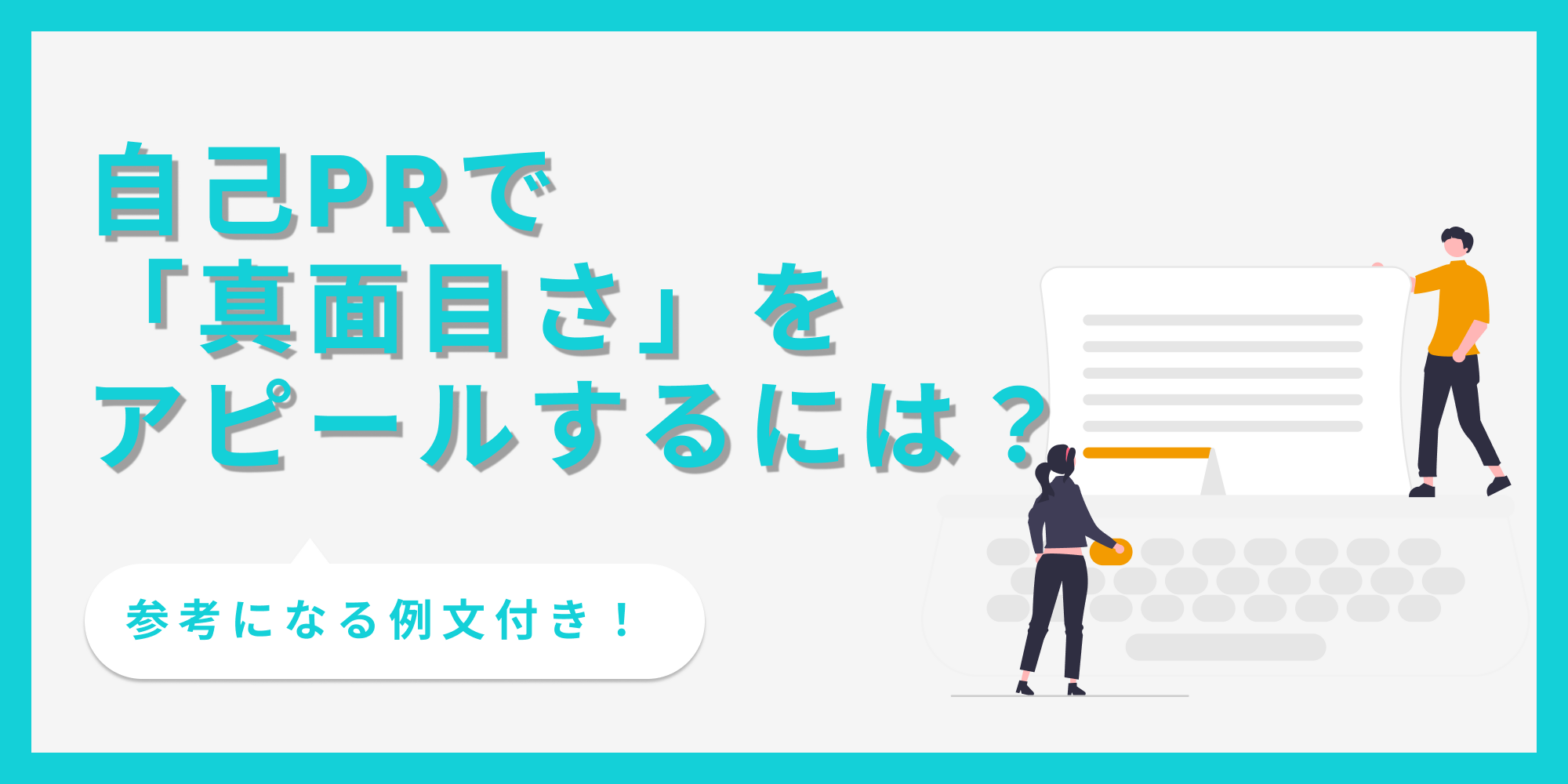






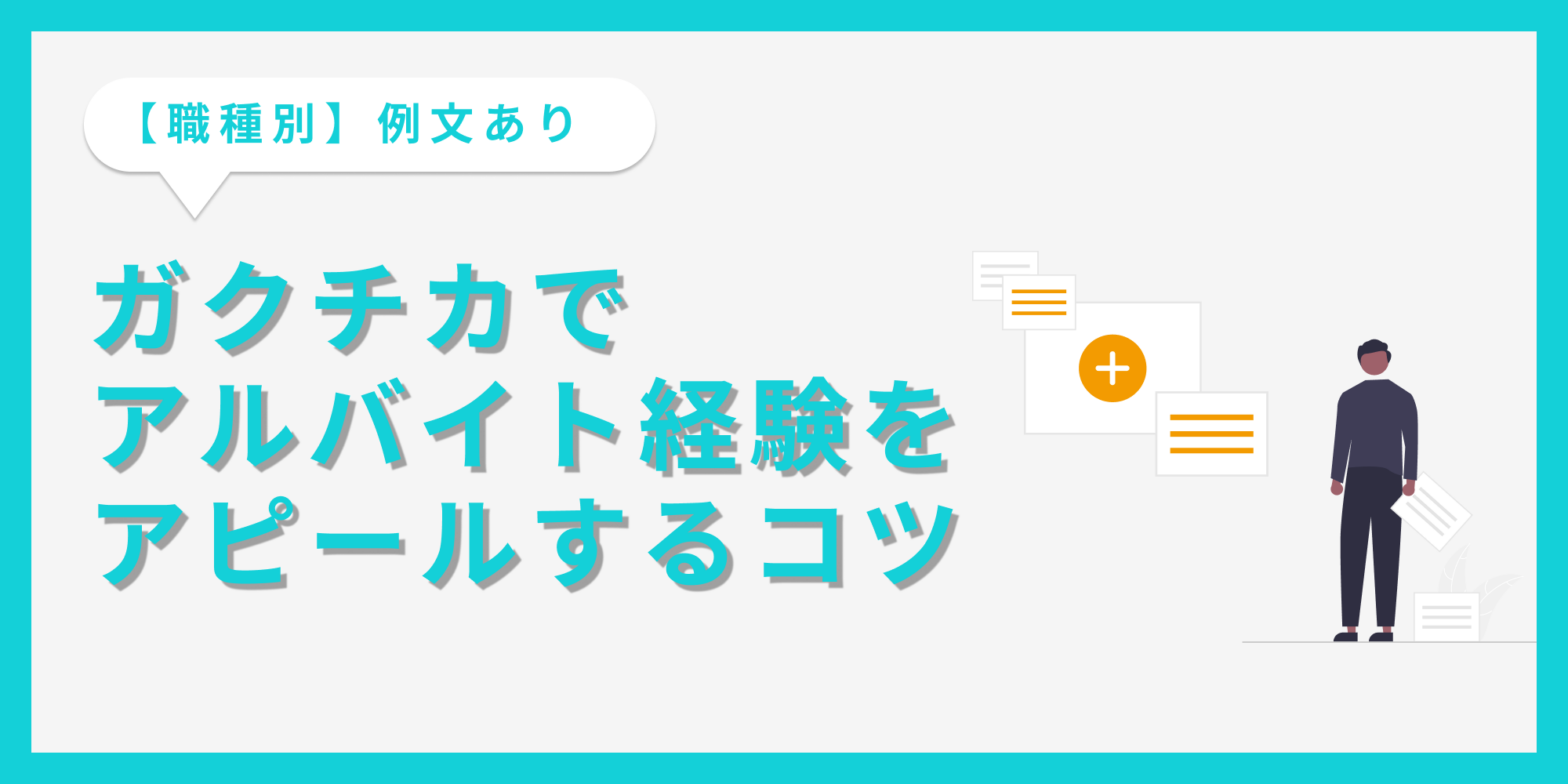



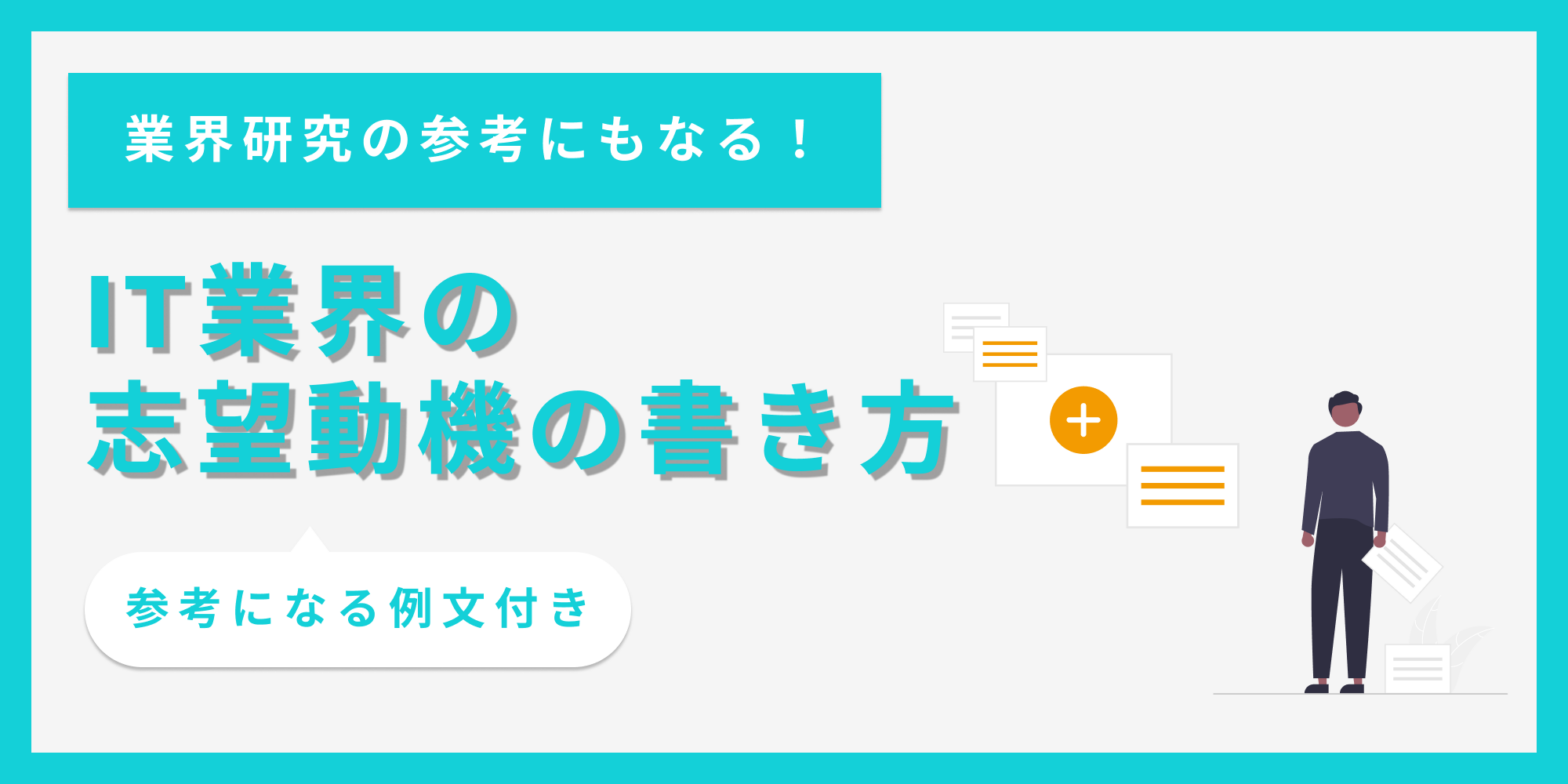



-1568x784.png)